医師への軌跡
新たな治療につながるような遺伝子異常を、
これからも発見していきたい
曽田 学

苦しむ患者をみて研究の道へ
父と父方の祖父が公衆衛生の医師、母方の祖父が山村地域の町医者という家に生まれ、小さいころから医師に憧れた。多くの人を救う研究、目の前の患者さんを治す臨床、どちらの良さも感じつつ、卒後すぐは臨床医を志し、市中病院で初期研修を受けた。その後、呼吸器内科のレジデントとなり、肺がん治療に携わるようになる。肺がんの末期で呼吸ができなくなり、苦しんで亡くなる患者さんを幾度もみては、心を痛めた。
ちょうどその頃、一部の肺がんに劇的に効く分子標的薬と言われる抗がん剤(イレッサ)が使われ始めた。しかしイレッサが効くのは、肺がんのうち特定の遺伝子の変異を持つ30%前後の症例にすぎない。イレッサが効かず、苦しむ患者さんにも、同じような「特効薬」を作れないか…。曽田先生は、肺がんの研究をしたいと思うようになっていった。
一丸となって論文を発表
当時の上司に紹介されて、2004年に自治医科大学の大学院に進学し、がん研究の第一人者である間野博行教授が率いる研究室で実験生活を開始した。取り組んだテーマは、手術で摘出した肺がんの検体を用いて、がんの新たな原因遺伝子を探すというものだった。
外科の協力を仰ぎ、自分で手術の日程を調べた。患者さんに承諾をもらい、アイスボックスを持って病理室まで検体を取りに行った。「同じものは決していただけないのだから、検体を絶対に粗末に扱うな」という教授の教えのもと、一つひとつの検体から丁寧にDNA、RNAを抽出し解析していった。
幸運なことに、研究開始からそう時を待たずして、新しい、そして世界を驚かすに値する遺伝子異常が発見された。新発見は、世界に先駆けて発表しなければ論文の価値が半減してしまうため、「とにかく早く論文に!」と研究室全体が一丸となって、発表に必要な実験を一気に進めた。2006年5月の発見から一年たらずで論文を仕上げ、2007年7月に『Nature』で発表。世界的に注目が集まった。
その時その時にできることを
発見から5年、この遺伝子異常を持つ肺がんへの新薬が開発され、日本でも認可された。投薬後1~2週間で劇的に症状が改善されるそうだ。この遺伝子異常を持つ患者さんは肺がん全体の約5%。少なく感じるかもしれないが、イレッサの適応にならない患者さんのうち約20%がこの遺伝子を持つ計算になる。その人々を新たに救うことができるようになったと考えれば、研究の成果は大きい。自分が携わった研究がたった数年で患者さんの役に立ち、新薬が多くの人を救うのを自分の目で見られることは、医師冥利に尽きる幸せだと曽田先生は言う。
「あの日にあの患者さんの承諾を取りに行かなければ、この発見はなかったかもしれない。本当に幸運や周囲の協力に恵まれていると思います。これからも、その時できることを精一杯やり、新たな治療に結びつくような遺伝子異常を見つけたい。そう思いながら研究を続けています。」
研究内容について~EML4-ALKがん遺伝子の発見と治療応用~
曽田先生が大学院生として所属した研究グループでは、間野博行教授を中心として、がん検体から効率良くがん遺伝子をスクリーニングする独自の手法を確立し、各種がん検体における遺伝子異常を探索していた。曽田先生が発見したのは、EML4とALKという遺伝子が融合する新しい遺伝子変異だった。この「2つの遺伝子が融合している現象」は血液がんでは知られていたが、肺がんのような固形がんにも生じるとは考えられていないものだった。BCR-ABLという融合型のがん遺伝子を持つ血液がんにはグリベックという劇的に効く分子標的薬があるため、この発見はEML4-ALK異常を持つ肺がんの新たな特効薬の開発につながると期待された。
実際に、アメリカのファイザー社がザーコリというALKの阻害剤の治験を始めたところ、優れた効果を示すことが確認された。この薬は2011年にアメリカで認可され、日本でも2012年に認可を受けるに至った。EML4-ALKの発見は、日本発の研究によってがん患者の命を救うことにつながった、エポックメイキングな出来事なのだ。
東京大学大学院医学系研究科生化学・分子生物学講座 細胞情報学分野*
1999年、聖マリアンナ医科大学卒業。初期研修・後期研修を関東逓信病院(現・NTT東日本関東病院)で行い、その後自治医科大学の呼吸器内科に大学院生として入局。2007年、『Nature』に肺がんの新規遺伝子異常に関する研究成果を発表、2011年度日本医師会医学研究奨励賞、2013年第1回後藤喜代子・ポールブルダリ科学賞を受賞している。
*取材時(2013年8月)は、自治医科大学分子病態治療研究センターゲノム機能研究部所属
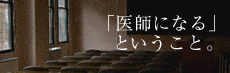


- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:曽田 学先生
- Information:October, 2013
- 特集:在宅医療 患者の「居場所」で行う医療
- 特集:ケース・スタディ 在宅医療の現場から
- 特集:医師・患者関係からみる在宅医療
- 特集:在宅医療に携わる様々な医師
- 特集:在宅医療を支援する仕組み
- 特集:スタディ・ツアーを終えて
- 同世代のリアリティー:芸術の分野で生きる 編
- NEED TO KNOW:患者に学ぶ(周期性ACTH-ADH放出症候群)
- チーム医療のパートナー:医療ソーシャルワーカー
- 10年目のカルテ:呼吸器内科 光石 陽一郎医師
- 10年目のカルテ:呼吸器内科 武岡 佐和医師
- 医師会の取り組み:沖縄県医師会医学会賞(研修医部門)
- 日本医師会の取り組み:産科医療と医師会
- 日本医師会の取り組み:医療における消費税問題
- 医師の働き方を考える:産科医としての臨床経験を活かし、公衆衛生の分野で管理職として働く
- 医学教育の展望:救急を基盤とした研修で大学と市中の両方を経験
- 大学紹介:弘前大学
- 大学紹介:山梨大学
- 大学紹介:愛知医科大学
- 大学紹介:熊本大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- 医学生の交流ひろば:3
- 医学生の交流ひろば:4

