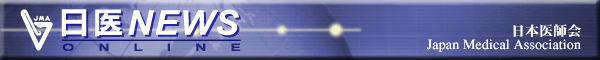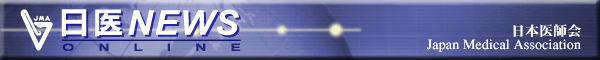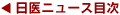 |
第1090号(平成19年2月5日) |
NO.39

告 知
秋吉久美子(女優)

 |
秋吉久美子(あきよしくみこ)
女優.静岡県出身.昭和49年に映画「赤ちょうちん」で注目を集め,以来,多くのテレビ,映画に出演している. |
季節よ待って,あるいは訪れないでくれ.
何と言う重たい日々であったことか.一昨年のお盆に母が倒れた.正確にはお盆でたまたま実家に帰った妹が,お風呂上がりの母の顔を見て,やけに黄色い,と気が付いた.母は,「あら,そうかしら?」と,のん気に返したが,妹の娘,私の姪が,「黄色いよ,おばあちゃん.すごい黄色い,変だよ」と押して,“念には念を”で,近所の主治医を訪ねた.
診察を終え,医師から,「ちょっとお話が……」,と呼ばれた妹は,「膵臓がんの疑いがありますね.大きい病院で検査することをお勧めします」とストレートに言われた.「どうしたの?」と尋ねる母に妹は,「大きい病院でちゃんと検査した方がいいって」とことばを濁した.それから去年の冬,二月の末に母が亡くなるまで,私たちは,母にいかに真実を隠し通すか,神経衰弱のカードゲームを,同じ顔ぶれでし続ける日々に突入した.家族がお互いの顔色をうかがいながら,お互いの一挙手一投足をとがめる.母に「がん」だと感付かれてしまうような間違いでもあれば,それは非難の的になった.
伝えられなかった真実
母に真実を隠すことは,大病院で病名が確定した時点で,私,私の息子,妹,妹の家族の数人で何度も話し合った結果だった.
がんが発見された時,厚さ一センチのすい臓に対して,母の場合は,すでにその三倍の三センチの直径だった.がんがすい臓より大きい.完全にがんがすい臓を蝕んでいる.
大病院の医師は余命六カ月以内と宣告した.手術を受けられる可能性があるかないかは微妙だが,検査入院で約一カ月,手術後の経過によっては,命が危ぶまれる場合もある.もし,手術が成功したとしても,身体は確実に弱り,もう二カ月ぐらいの入院が必要.そうすれば六カ月よりも余命が多少伸びるかもしれない…….何と言うことだろう.絶望的だった.
命が助かるという勝利をまったく期待できない戦いに,母を送り出すのか.精神的な絶望や肉体的な苦しみを,これから死ぬまでの六カ月間,与えるのか.告知をし,検査をし,手術をし,最悪の場合はそのまま命を落とすか,あるいは退院後一カ月,二カ月の小康状態の後,決定的な死を待つために再度入院ということになる.つまり普通に暮らせるのは約一カ月,しかも弱りきった身体で.私たちは“せめて”という願いのもとに,一つの選択をした.
ステントを入れて,まずは胆汁を流し,黄疸を取り,母を退院させる.そうすれば,少なくとも四カ月か,五カ月の人生を母に与えられるのではないか.せめて精神の苦しみは救ってあげたい.“告知せず”に決めた.医師にもその旨を伝えた.母には,全員が協力して“胆管炎”という病名であると伝えた.
「胆管が炎症を起こして,どうにもうまく胆汁が流れない.まあ,長い付き合いになってしまう病気なんだけど,みんなでうまくやっていこう.ただ,もう一人で生活するのはムリです.いつまた胆管炎から黄疸になったり,糖尿病,敗血症に至るかもしれない」
オブラートにくるんで言ったつもりだったが,母はそれだけでも怯えて,機嫌が悪くなった.何しろ,風邪で寝込んだこともない人である.頭が痛いということもなく,過ごしてきた人である.「胃が痛いって,どういうことなのかしら?」と言っていた.七十二歳だが,マニュアルの車で高速道路を飛ばし,私の息子が使っていた,ハンドルがT字の自転車で坂道を走って買い物に行っていた.やはり,本当の病名の告知は,どうしても無理だなと思った.
しかも,私たちは,父も三年前に肺がんで亡くしている.父の場合は,自宅療養で往診という形をとった.昭和の初期のドラマのように,父が布団の上で息を引き取るのを私たちは見守り,白衣の医師がやってきて脈を取り,臨終を確認した.
母は介護で心を痛め,十五キロ痩せた.たった半年の間に.そして,「あなたもその“がん”なんですよ」とは,とても言えなかった.
また,父の場合には,いきなりレントゲン写真を見せられ,「このテニスボール大のモノが“がん”ですね」とあっさり告げられてしまった.父は繊細な人で,男のプライドもあり,強く見せるために,ほとんどやけになってしまった.
母の場合は,「すい臓がんは普通,ノド飴程度なのですが,ほとんどゴルフボール大になってますよ」と告げれば良いのか? できる訳がないじゃないか.
人生の最後に会う人
私たちの素人芝居を,多分,母は信じようとした.東京に連れて来るのは,とても難しかった.母が新しい病院を恐れたからだ.年をとると,慣れている環境を離れるのは億劫だ.だが,家族のフットワークを考えると,それしかなかった.幸いなことに,格式ばっていない病院,そして患者にとって信頼できる素晴らしい医師に,世田谷で出会った.私にとっては,今までの仕事の何よりも大きなプロジェクトだった.失敗は許されなかった.
K中央病院と,外科医のO先生に母を受け入れてもらうことにした.病名は“胆管炎”.私とO先生はカンファレンスルームで,あるいは真夜中の廊下でよく話し合った.次々と起こる合併症,経過,その先の予測.O先生は,もちろん医師の立場で告知を勧めた.告知にはタイミングがある.言い方もある.当て逃げのような乱暴なやり方はいけないが,医師の伝え方や家族の支えによって,患者は意思を持って乗り越える.「僕だったら,死ぬ前に真実を知っておきたいけどなあ」と,人生論のような話にまで及んだ.「日本には宗教観はあっても,宗教と人生が強く結び付いているとは言えません.宗教の支えなく死を受け入れるのは,辛すぎます」と私は言った.結局,入院の最後のころ,「私は死ぬの? 私の病気は本当は何なの」と執拗な母に,最後まで嘘をつき通すのが愛情なのか,真実を伝えて人間としての尊厳を守るべきか,迷った末,「もしかしたら治らないかも知れないが,だれにでも起こり得るのだから,今から死を考えるのは,治ったとしても役に立つはず.いいチャンスだから,今のうちに考えておこう」と伝えた.
それから母は,生きる希望と死ぬ恐怖に素直になった.それは良いことのようにも,悪いことのようにも思えた.母が強ければ受け入れ,弱ければ打ち崩される.人生の最終章の嵐の日々に変わった.
もし,病院のスタッフや医師の,客観的で,和やかな受け入れ態勢がなければ,とても家族だけでは乗り切れなかったと思う.O先生が穏やかな口調で言っていた言葉を,今でも思い出す.
「人は祝福されて生まれてきます.が,どんなに成功した人でも,あるいは恵まれない人生を送った人であっても,ほとんどの人が病院で死を迎えます.人生の最後に会うのは,私たち医師や看護師なのです.そこをよく分かって,私たちは患者に接するべきだと思います」
|