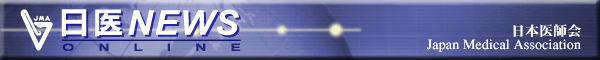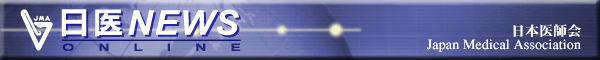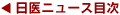 |
第1139号(平成21年2月20日) |
日本医師会賞
『医は仁術』
平野 洋子(ひらのようこ) 神奈川県 46歳・旅館業

数年前,その女性はさっそうと現れた.白いベンツに乗って,流行のブランド品に身を包み,メークにもすきが無かった.
東京生まれの東京育ちで東京の医大を卒業した三十代の医学博士は,私の住む小さな町の小さな病院に,胃腸外科医長として赴任して来たのだった.
私も両親も,昔からその病院がかかりつけで,三十年近くにわたり我が家の主治医だった医師が高齢で退任した後にやって来た若い女医に不安を抱いた.「あんな現代っこで大丈夫かしら」.母がそうこぼしたのを覚えている.
何しろそのころの父は,体中悪くないところが無いような状態で,年に二,三度はその病院へ短い入院を繰り返していたからだ.特に心臓疾患は深刻で,発作を起こした時の用意にと,常に舌下錠を携帯していた.
その父が胃の変調を訴えたのは,二〇〇五年,八十一歳の時だった.
彼女はすぐに粘膜にがん細胞が点在した初期の胃がんと診断した.母と私が呼ばれ,「手術自体は簡単なものです.けれどお父様のご年齢と心臓病を考慮すると,開腹手術はかなりお体に負担をかけると思います.今は胃カメラのように口から内視鏡を入れて胃の粘膜ごと取ってしまうことができます.私も何度かやりましたが,この病院の設備では不十分なので,もしよろしければ大学病院を紹介しますが,どうしますか」という説明を受けた.
大学病院での内視鏡手術の日,父の病室に彼女がひょっこり顔を出した.「有給休暇を取って来ました.ここの病院には話をつけてありますので,私も手術に立ち会います」
私はその時初めて,彼女の医師としての責任感の強さと優しさに気付き,彼女の外見だけで判断をしていた自分を恥じた.
父の手術は無事成功し,自宅療養をしていた時のことだ.ある晩,ひどくおなかが痛むと言い,トイレに行った父は大声で母を呼んだ.父のおなかから出たものは便ではなく大量の血液だった.
すぐに町の病院へ電話を入れ,タクシーで父を連れて行くと,夜の十一時を回っていたにもかかわらず,出迎えたのは彼女だった.父の主治医として病院から連絡が入った彼女は,私たちよりも早く病院に駆け付け,待っていてくれたのだ.
下血の原因は,手術の傷口から少しずつ流れ出た血液が,心臓の薬のために凝固せずにおなかの中にたまってしまい,それが一度に下りたのだろうということだった.彼女の適切な処置で父は一命を取り留めた.
それからの二年間,父は彼女が処方してくれる飲み薬で落ち着いた生活を送っていた.
二〇〇七年,父は自宅で突然倒れた.意識はあるのだが,ろれつが回らない.迷わず救急車を呼び町の病院へ運んだが,玄関先で父の姿を見た彼女は,「心臓発作じゃありません,脳梗塞(こうそく)です.うちの病院ではどうしようもないので,このまま脳外科へ回ります」と言うと,脳外科への連絡と救急隊員への指示を素早くこなし,一緒に救急車へ乗り込んでくれた.
ちょうど午前の外来が終了し,昼食をとるところだったらしいのだが,そんなことはおくびにも出さず,父に付き添ってくれた彼女に,私は心の中で手を合わせた.
救急車の中で次第に意識の薄れていく父に向かって,母が「もうすぐいつもの病院に着くから安心してね」と大きく何度も声を掛けた.彼女も一緒になって,「大丈夫ですよ,またすぐに楽になりますから」と言った.
かすかにうなずいた父はそのまま意識を失い,到着した脳外科の集中治療室でも,一度も意識が戻ること無く,二日後に亡くなった.
八十四歳の,あまりにもあっけない最期だった.
お通夜に来てくれた彼女は泣いていた.
私は,「本当にお世話になりました.先生のお陰で父は安らかに眠ることができました.ありがとうございました」と深々と頭を下げた.
私は今でも,父は自分がいつもの病院で主治医に見守られながら旅立ったと信じていると思う.なぜなら父が最後に聞いたのが,母の「いつもの病院へ行くからね」と,彼女の「大丈夫ですよ」という声だったからだ.
“医は仁術”.彼女の医療はまさにそれを地でいっている.小さな町の小さな病院は,今日も彼女の診察の順番待ちの人であふれている.
|