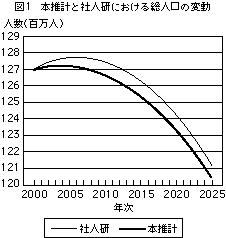
日医ニュース 第990号(平成14年12月5日)
| 資料版 人口・経済・社会保障モデルによる長期展望 ―人的資源に基づくアプローチ― 日医委託調査研究 |
| 小川直宏日大経済学部教授(日本大学人口研究所)は,1982年以来,人口,経済,社会保障の3部門を多数の変数で結ぶというまったく新しい推計方法である「長期人口経済モデル」を開発し,将来推計人口を発表してきた. 今回の「人口・経済・社会保障モデルによる長期展望―人的資源に基づくアプローチ―」のポイントは,以下のとおりである. |
(1)総人口のピーク値は2005年
2000年の国勢調査では,日本の総人口は1億2693万人.日大人口研の新人口推計で,日本の総人口のピークは2005年1億2745万人,国立社会保障・人口問題研究所(社人研)の今年1月発表では2006年,本推計より1年後になっている.ピーク値は近似し,社人研推計が29万人上回っている.
本推計の最終年次である2025年の総人口は1億2029万人.社人研推計はこれを105万人上回っている.(図1)
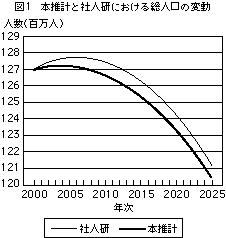
(2)合計特殊出生率が2017年に1.24まで低下
2000年の合計特殊出生率(1女性が生涯に産む子どもの数)は,1.36(人)だった.推計では,2017年に1.24まで低下し,2025年までその水準を維持する.
社人研推計の最低値は2007年の1.31で,本推計より0.05高く,2025年は1.38になっている.(図2)
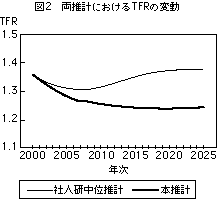
(3)65歳以上人口の割合は2025年に31.04%に
2000年国勢調査による65歳以上の高齢人口は2204万人,総人口の17.37%だった.本推計では,2025年に3727万人,総人口の31.04%に達する.社人研推計の同年の高齢人口は3473万人,総人口の28.7%で,本推計の方が人口高齢化の進行が著しい.
(4)2003年に高齢化率は日本が世界一
国連の世界人口推計に基づき,日本の高齢化率を計算すると,2003年にイタリアを抜いて世界一になる.さらに本推計による2025年の高齢化率を,世界人口推計の2025年のデータと比較すると,日本は31.04%でトップ,次いで2位はイタリアの25.7%,3位はスウェーデン24.4%.
(5)2025年の女性の平均寿命は89.44年,人生90年時代へ
厚生労働省による2000年の平均寿命は,男子77.64年,女子84.62年だった.本推計によると,平均寿命は今後も延び続け,2025年には男子83.85年,女子89.44年になる.
社人研推計の2025年の平均寿命は男子79.78年,女子87.52年である.
(6)2023年に人口の半分以上が50歳以上に
人口の年齢中位数は,2000年では男女計で41.5歳であるが,2023年には50歳を超え,2025年では51.1歳となる.男性は2000年の39.8歳から2025年では50歳となり,女性は2000年で43.1歳から2018年で50歳を超え,2025年では53.3歳となる.(図3)
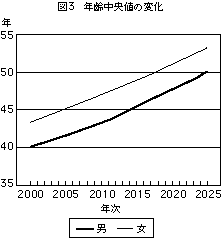
(7)加速する高齢化のスピード
65歳以上の割合が10%から20%となるのに要する年数は,本推計では1984年から2005年の21年.国連世界人口推計ではカナダが40年,イタリアとギリシャがそれぞれ41年となっており,日本は世界一のスピードである.
(8)オールド・オールドの割合の急増
65歳以上人口に占める75歳以上人口(オールド・オールド)の割合は,2000年の39.9%から2025年には59.61%となり,「高齢者の高齢化」がいっそう進み,要介護人口の増加が介護負担の増大を誘発する.また,2021年では高齢人口に占めるオールド・オールドの割合が50.2%となり,ドイツの49.0%を抜いて,世界一の水準になる.
(9)家族による介護能力は,2005年に世界最低,25年間で半減
65〜84歳の高齢者1人に対し,成人介護適齢期女性(娘や息子の嫁)が何人いるかという比率をみると,1990年の1.298から2015年には0.588まで低下し,人口サイドから見た「家族扶養能力」が25年でほぼ半減する.社会的な介護施策である介護保険制度の充実と合わせて地域での高齢者支援がいっそう必要になるだろう.2005年には0.77となり,世界で最も低くなる.
(10)少子化から長命化が高齢化の主要因に
高齢化に与える要因のうち,(1)出生率による影響(2)死亡率による影響―に着目して,相対的インパクトを調べた.2000〜2005年は102.4で,出生率の高齢化に与える影響は大きかった.
しかし,2005〜2010年は96.1,2015〜2020年は95.2,2020〜2025年は93.7と,死亡率の影響の方が大きくなっている.高齢化のプロセスを決定する要因として,今後は寿命の限界や高齢者の死亡率の改善なども注目すべきである.
(11)介護ニーズが“外出”から“トイレ”へ
65歳以上の高齢者のなかで介助が必要な人が今後増大し,その内容も“電車・バスに乗る”や“ショッピングに行く”という外出型から,“食事やトイレ”といった身近なものへとシフトする.
| 2000年(万人) | 2025年(万人) | 年平均増加率(%) | |
| 労働が困難 | 1170.3 | 1713.7 | 1.54 |
| 風呂に入るのが困難 | 124.4 | 325.5 | 3.92 |
| 服を着るのが困難 | 93.2 | 242.2 | 3.89 |
| 食事をとるのが困難 | 43.4 | 121.3 | 4.20 |
| ベッドから立つのが困難 | 67.9 | 171.3 | 3.77 |
| トイレが困難 | 65.0 | 175.8 | 4.06 |
| 買い物が困難 | 185.4 | 437.5 | 3.49 |
| バスや電車が困難 | 218.4 | 519.6 | 2.38 |
(12)高齢者を“ASSETS”とする社会の構築へ
65歳以上の高齢者人口のなかで健康である割合が2000年の82%から2025年には75%へと減少するが,絶対数としての健康高齢者が1059万人から1713万人に増加するので,これら健康な高齢者を“ASSETS”として考える社会の構築が急務である.