 |
第1012号(平成15年11月5日) |
NO.1 ―新企画―

ヒポクラテスの誓いと,社会的共通資本としての医療
宇沢弘文(日本学士院会員,東京大学名誉教授)

今号からはじまる新企画「オピニオン」は,各界の有識者から日医会員へのメッセージである.
1回目は,医療を国民の共通財産として大事に管理していくべきであるという,宇沢弘文氏による「社会的共通資本」論をお届けする.
(なお,感想などは広報課までお寄せください)
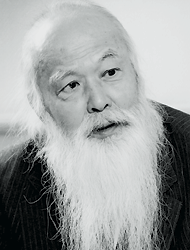
宇沢弘文(うざわひろふみ)
同志社大学社会的共通資本研究センター長.東京大学名誉教授,日本学士院会員.昭和26年東京大学理学部数学科卒業.カリフォルニア大学助教授,スタンフォード大学準教授,シカゴ大学教授などを経て,昭和44年東京大学経済学部教授.元世界計量経済学会会長.全米科学アカデミー外国人会員.文化勲章受章.主著書/宇沢弘文著作集[12巻](岩波書店). |
つい最近までは,医学校を卒業して,医師としての道を歩み出そうとするとき,ヒポクラテスの誓い,あるいはそれに準ずる誓いを誓うことが義務づけられていた.現在では,このような形式的な儀式は必ずしも一般的ではなくなったが,各人がそれぞれ,ヒポクラテスの誓いの精神を自らの心に深く刻み込んで,医師としての職業を全うすることを誓うのは,洋の東西を問わず,職業としての医師を志すときに,もっとも重要なこととされている.
しかし,現実に医師が医療行為を行おうというとき,ある医療機関に属して,さまざまな医療機器,医薬品を使い,看護師,検査技師をはじめとするコメディカル・スタッフの助けを借りなければならない.医療施設を管理,維持するために必要な人的費用,光熱水料などの維持費,さらに医療施設の建設,医療機器の購入に伴う資本的経費を必要とする.また,医師自らの医学的知見を常に最新なものとし,新しい医療技術を修得するためにも多くの時間,労力,費用を必要とする.
そして,医師もまた一人の人間である.家庭を持ち,子どもを育て,自らの人間的資質の再生産,さらには老後の生活の準備をしなければならない.このような諸々の費用を考慮に入れたうえで,それぞれの医療機関の経営的なバランスが維持されなければならない.
このとき,ヒポクラテスの誓いに忠実に医療を行ったとき,医療機関の経営的安定,あるいは個々の医師やコメディカル・スタッフの生活的安定を維持することができるであろうか.医学的最適性と経済的最適性とは両立可能であろうか.この設問に答えるのが,社会的共通資本としての医療の考え方である.
安定的な社会を具現化するための社会的共通資本
社会的共通資本は,一人ひとりの市民の人間的尊厳を守り,魂の自立を保ち,市民的自由が最大限に確保できるような社会を形成するために基幹的な役割を果たすものである.いい換えれば,社会的共通資本は,一つの国ないしは社会が,自然環境と調和し,優れた文化的水準を維持しながら,持続的な形で経済的活動を営み,安定的な社会を具現化するための社会的安定化装置といってもよい.
社会的共通資本はどのような所有形態をとろうと,その管理,運営は決して官僚的基準に従って管理されてはならないし,また,儲かるか否かという市場的基準によって大きく左右されてはならない.それぞれの社会的共通資本にかかわる職業的専門家集団によって,専門的知見と職業的倫理観に基づいて管理,運営されなければならない.個々の社会的共通資本,特に,医療と教育についてみると,大きな経常的,資本的赤字が発生するのが一般的であって,それは原則として,基本的には税収によって補填されるべきで,補足的に社会保険制度などを通じて処理される.
日本の医療制度は社会的共通資本として望ましいか
ひるがえって,現行の日本の医療制度を考えてみたとき,果たして社会的共通資本としての医療という観点から望ましい制度であろうか.
需要面からみるとき,社会保険制度が,ある程度,社会的共通資本としての医療の理念を具現化したものであったが,近年,もっぱら財政的な動機に基づく制度改悪が行われて,その理念的な側面が大幅に崩れつつある.
供給面からみるとき,日本の医療制度は,矛盾に満ちている.よい医療を供給しようとすると,その病院は経営的に極めて困難となる.その主な原因は診療報酬制度にある.医師,看護師などの技術料が極端に低く抑えられている反面,医薬品,検査機器が異常に高価に設定されていて,過剰ないしは無駄な投薬,検査が一般化し,その結果として,医療の実質的内容を大きく歪め,医師の職業的倫理の維持,専門的能力の発展に大きな障碍となっている.
市場的基準によって,左右されてはならない診療行為
日本の医療制度の改革が,現在もっとも緊急度の高い政治課題であることは,国民の多くが共通して持っている認識である.しかし,それは,診療報酬点数表の改正,健康保険制度の手直しなどの微縫策によっては解決できない.より根元的な解決の道が求められている.
まず,現行の診療報酬制度を改革して,医師が医学的見地から最適と考える診療行為を行ったとき,各医療機関が経営的に可能になるようなものにしなければならない.その際,問題となるのは,各医療機関ないしは個々の医師が,高い職業的能力と倫理観を持ち,常に医学的見地から最適と考える診療行為を行っているか,さらに,医療資源が効率的に配分されているかをどのようにして判断するかである.これは,決して厚生官僚が行政的観点から行うものであってはならないし,ましてや儲かっているかどうかという市場的基準によって左右されてはならない.
医療の財源については,国民健康保険,老人医療,介護保険の制度を参考にしながら,広く一般の方々の考えを聞いて,慎重に決めるべきである.このとき,欧米の先進諸国の例に倣って,所得税の一部を各個人の選好に従って,ある特定の病院や学校に対する寄付に当てたり,あるいは病院や学校に対する相続財産の遺贈は全面的に非課税とすることが望ましい.後者の税制特別措置は現に存在はするが,厳しい行政的な条件が付けられているだけでなく,一年以内に使い切らなければならなくなっていて,基金として組み入れることは認められていない.
いずれにせよ,今,もっとも望まれていることは,現行の医療制度を,医学教育,研究の面も含めて,徹底的に改革して,医学的最適性と経済的最適性とが両立できるような制度を実現することである.
|

