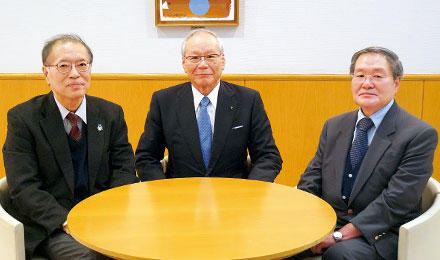
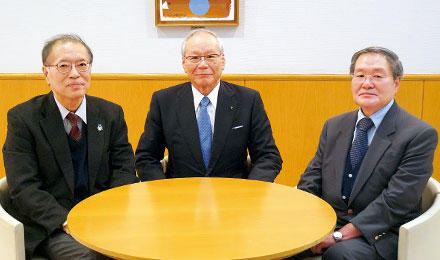
| 人生100年時代と言われる中で、今号では大内尉義虎の門病院院長/東大名誉教授(写真・右)、樋口範雄武蔵野大学法学部特任教授/東大名誉教授(写真・左)をお招きし、横倉義武会長と共に、高齢者医療にどのように対応していくべきか、高齢者の定義や終末期医療の課題等に触れながら、語り合ってもらった(日医会館にて3月6日に実施)。 |
|---|
横倉 お忙しいところ、本日はありがとうございます。
人生100年時代と言われる中で、高齢者にどのように対応していくかが大きな課題になっています。
本日は、お二人と日本の現状を共有するとともに、その解決策についてもお話しできればと考えていますので、よろしくお願いします。
まず、高齢者とは何歳からの人達のことをいうのか、お伺いしたいのですが、日本老年学会と日本老年医学会では65歳ではなく、75歳からでいいのではないかという提言を出されていますが、大内先生、その背景などについて、お話し頂けますか。
大内 65歳以上を高齢者というのは、日本を含め多くの先進国の定義です。これは、昭和31年の国際連合の報告書で65歳以上の人口が7%を超えた社会を「高齢化社会」と呼んでいることが根拠になっています。
昭和31年以降、世界中の先進国では急速に高齢化が進みました。その要因として、例えば医療事情や食糧事情が良くなったこと、上下水道などの社会インフラが整ったことなどが挙げられます。健康にプラスとなるさまざまな要素があって、皆さんお元気に過ごせるようになったわけです。
そういった中で、高齢者が65歳以上という定義が今の社会の状況にマッチしていないのではないかという実感は多分、皆さんもお持ちであったのではないかと思います。
それでは、どのぐらい若返っているかを科学的に調べてみようということが、そもそもの出発点でした。それで、例えば、歩行スピードなどの体力、知的機能、残っている歯の数など、いろいろなコホートスタディの結果を見てみました。
すると、以前に比べて少なくとも5年、長ければ20年ぐらい、平均的には10年若返っていることが分かりました。その結果に基づき、65歳以上よりも、75歳以上を高齢者と定義した方が実情に合っているのではないかということで提言したわけです。
私達が、75歳以上が高齢者と定義したこの提言で一番申し上げたかったことは、65歳を過ぎても皆さんが昔よりも元気なのだから、元気なうちは社会的な活動をしようということです。
横倉 生産年齢人口の年齢を75歳まで上げれば、社会を支える側、支えられる側の比率も変わりますし、大きな意味がありますね。
大内 はい。65歳を過ぎたら、一夜にして「支える側」から「支えられる側」になるというのは、あまりにも形式的過ぎておかしいのではないかと思います。社会参画をいつまでも続けることができれば、その方の健康にもいいわけです。
しかし、気を付けなければいけないのは、高齢者を75歳以上とした時、その年齢以下でもフレイルの方はいますので、そういう方にはきちんと社会保障を手当てすることが必要です。もちろん、元気で働く意欲のある方には若い世代の負担を減らすという意味でも働いてもらいたいと思います。
横倉 同感です。樋口先生、今のお話について、いかがでしょうか。
樋口 私も大賛成です。日本社会は、少子高齢化をどうしても悲観的に考えがちですが、高齢者にもさまざまな方がいますし、64歳までが「支える側」で、65歳以上の方は皆「支えられる側」だという類型的な考えを少し発想転換すれば、日本だってまだまだ十分他の国に引けを取らない活力のある国と言えるのではないかと思います。
明るい高齢社会にするために

横倉 やはり、明るい高齢社会を日本がつくれるかどうか世界中が注目していますし、そのモデルをしっかりと示していかなければなりませんね。
先日、札幌から朝一番で東京に戻らなければいけないことがあり、朝早く空港に行ったのですが、お土産屋さんの販売員の多くが高齢の方達でした。その時間帯は高齢者に職場を提供していたのですね。
特に、これからは働き方改革を進めなくてはなりませんから、こういう働き方が広がっていけばいいと思います。
樋口 先週見たテレビでも、高齢者を優先して採用している会社が取り上げられていました。今後そういうことが大きく取り上げられるような流れが、益々増えていくと思います。
大内 ただ、今の日本の社会は、55歳とか60歳や65歳を定年とすることを前提につくられた社会ですので、その社会の仕組みを変えていかなければいけないと思います。
それから、体力的には、若い人のようにはいきませんので、どのような働き方ができるのか、そして給与体系をどうするのかといったことを国民的に議論して欲しいと思います。
横倉 やはりいろいろな人がいますし、高齢者の定義はフレキシブルにということですね。
樋口先生は、日本で初めて高齢者法についての講義を東大で行われたとお聞きしましたが、その背景にはどのようなことがおありになるのですか。
樋口 初めてということではないかも知れませんが、まず、高齢者に関わるさまざまな問題を取り上げてみようというのがありました。日本は超高齢社会ですし、日本の社会を取り上げる時に、高齢者の問題は大きな基軸になるだろうと考えたからです。
超高齢社会において、大きな課題としては三つあって、一つは"医療、健康"ですね。次に"住まい"で、高齢になってどこで暮らしていけるか。毎日のことですから、どこに住むかは重要です。最後にそれらを支えるための"お金"です。
それらの中でも、一番大事なのは"医療、健康"です。それに従って住まいも自ずから変わってきますしね。"お金"に関しても結局、亡くなるまでにどれだけの医療費が掛かるのか、更にどういうリスクがあり、そのリスクを避けるために何をやってはいけないかといった話が重要になると思います。
横倉 大内先生、虎の門病院では「高齢者総合診療部」を立ち上げたそうですね。
大内 虎の門病院では、2代目院長である沖中重雄先生が、日本の基幹病院で初めて臓器別の診療を始められました。
その頃は高齢者が今ほど多くなかったわけですが、高齢化が進んで、フレイルや複数の臓器に病気を患っている高齢の患者さん達が増え、臓器別の診療では対応が難しくなってきたわけです。
ところが、それに対応できる診療体制が一般の病院にはあまりないことから、高齢者の総合診療を実践する組織として「高齢者総合診療部」をつくりました。
その特徴は、医師・看護師だけではなく、薬剤師、医療ソーシャルワーカーや栄養士など、多職種の者達で高齢者の問題に立ち向かっていることが挙げられます。
その対象は、いわゆる臓器別の診療体制で対応できない、例えば老年症候群といったもので、高齢者の身体全体を社会的な状況も含めて総合的に診る医療を展開しています。入院ベッドは持たず、複数の診療科からコンサルテーションを受け、それに対してアドバイスをするといった横の連携で医療を提供しています。
こうした虎の門病院の取り組みがうまくいけば全国に発信できるだろうと考えており、頑張っていきたいと思います。
横倉 樋口先生、今のお話を聞かれて、いかがですか。
樋口 今、大内先生がおっしゃったように、高齢者はいろいろと病気を抱えている人が多いので、一カ所で総合的に診てもらえるというのは本当にありがたいことです。そうすれば、開業医の先生方が総合的に医療を提供しているところに紹介もできるわけですから、全国的に充実させることが今後重要になると思います。
それと同時に医師の世界だけではなく、日本の社会全体でも新しいものの見方をしていく必要性を感じました。
横倉 我々も、大内先生が提唱されている高齢者のフレイル予防が重要との考えにのっとって患者さんを診ることを勧めているのですが、改めてこのフレイル予防の重要性について、お話し頂けますか。
大内 高齢者は、加齢とともにいろいろな身体機能が衰えて、食が細くなり、だんだん歩けなくなるというイメージがあると思います。今までは、そういった状況を予防したり、早くから介入すれば、元に戻る可能性があることが全く認識されていませんでした。
そういった高齢者の状況は「虚弱」と表現されてきましたが、いかにも言葉の印象が良くない。それで、「虚弱」とか、もろさを表す英語の「Frailty」を参考として、「フレイル」とすることにしました。
このフレイルには、身体的なものだけでなく、精神・心理的なものもありますし、社会的なものもあります。そういう多面性のある概念を打ち出して、その予防・介入の重要性を強く提唱していこうとしたわけです。
このフレイルという概念は、医療関係者には短期間で浸透しましたが、まだ一般の国民にそれほど知られていないことが問題だと思っています。
横倉 フレイルの予防には、栄養と身体能力と精神的なもの、それと社会参加という四つのファクターが大きいと思うのですが、いかがですか。
大内 はい。おっしゃるとおりだと思います。
横倉 社会参加という意味で、樋口先生は高齢者の義務教育化を提唱されているそうですね。
樋口 そうですね。提唱と言えるほど立派な話ではないのですが、やはり日本は教育により成り立ってきた国だと思うのです。そういうことを考えますと、大学まで進む方が多くなっても、その教育までで後の人生は大丈夫なのかという話はあると思います。
そうだとすると、人生ずっと学び続けるような仕組みをつくってあげた方がいいのではないか。
特に、高齢者が退職して何をして過ごすかが問題となる際に、その準備として、こういう過ごし方もありますよということを教わる機会が必要だと思うのです。
義務付けというのは、法律的発想などと言われそうですが、そうすることで、後から背中を押すというか、悪いことではなく、義務だから仕方がないといって皆さんやってくださるのではないかと......。制度が社会を変えていくのではないかと思っているところです。
横倉 社会参加の大きなファクターですね。
大内 社会参加を続けている方は、認知症の発症率も低いですし、フレイルになる率も低いことが実証されていますので、良いことだと思います。
樋口 社会参加をすることは社会のためだけでなく、自分のためにもなるということですね。
大内 そういうことですね。義務教育化がいいかどうかは分かりませんけれども、社会的なインセンティブをつけるということは考えられますよね。
樋口 そうですね。
横倉 認知症の話が出ましたが、認知症の方が2025年には約700万人になるとの予測もあります。何とかそうならない社会環境もつくっていかなければなりませんね。
大内 おっしゃるとおりだと思います。
横倉 認知症に関連して、意思決定が難しい高齢者が増えてくると、医療代理人が必要になるという話も聞かれます。
我々が医療を提供する際に、どうしても本人の同意が必要な場合もあります。そういった時に、代理の方にお願いできればと思うのですが、その辺りは樋口先生いかがですか。
樋口 突然倒れることももちろんあるわけで、自分だけはそうならないということはないですからね。
ですから、そうなる可能性を意識して、何らかのプランニングをしておく必要があります。そのプランニングの一環として、最終的には自分で決めたいけれども、信頼できる代わりの人をあらかじめ決めておくと、本人が倒れた時に、家族、そして医師も助かります。そのため、諸外国では(自分が意思表明ができなくなっても法的な効果があるという意味の)持続的代理権法が広まっています。
一方、これも私の偏見かも知れませんが、日本は意外と他の人に頼れない。誰かに代わってやってもらうことをあまり得意としない社会だと思うのです。
しかし、病気になったら自分では話せなくなるかも知れませんし、そういう仕組みをつくっていくことで社会全体が生きやすくなると考えています。
横倉 今の点については、大内先生いかがですか。
大内 医療の現場で困るのは、インフォームド・コンセント(IC)の際に患者さんが認知症である場合です。また、認知症の診断がついていなくても、認知機能が低下している方がかなりおられると思います。そういう時に医療現場でどう対応するのかということを、医学と法学の専門家が力を合わせて指針をまとめる必要があると思っています。
患者さんの死は敗北ではない

横倉 日医の会内委員会の生命倫理懇談会では、平成28年度の諮問「超高齢社会と終末期医療」に引き続き、今期は、「終末期医療に関するガイドラインの見直しとアドバンス・ケア・プランニング(ACP)の普及・啓発」について検討してもらっており、樋口先生は懇談会の副座長でいらっしゃいますので、ぜひ、この問題についてもご示唆を頂ければと思います。
終末期医療についてもう少しお話をお聞きしたいと思いますが、樋口先生、以前、講演で『死すべき定め』という本の話をされておられましたね。早速、私も読ませて頂いたのですが、その本について、少しご説明頂けますか。
樋口 この本の執筆者は、ハーバード大学の提携病院で研修医もしているインド系アメリカ人の外科医ですが、内容は『The New Yorker』という雑誌に連載していたものをまとめたものです。
アメリカでベストセラーになっており、特に医師の方々に大変好評だったと言われているそうです。
"始め"の部分で、自身が外科の研修医時代に、もう治らない患者さんを担当した際の逸話が書かれています。その患者さんが終末期にいろいろな臓器が悪くなり、ある臓器だけなら治せるということで、「全体としてあなたは治らないんですよ」ということを言わずに、ICをして、患者さんが納得の上で手術をするのです。手術は成功するのですが、患者さんに笑顔が戻ることはなく、苦しみ続けて亡くなりました。そうした中で、この医師は「自分がやったことは何だったのだろう」と思うわけです。
当たり前ですが、人間は生物だからいずれ亡くなるわけで、まさに「死すべき定め」なのですが、最近では、クオリティ・オブ・デスということまで言われるように、良き死に方をしたいと思うのではないでしょうか。その際に、良き死に方というのはどういうものなのか、ただ医療機関に運んでもらえばいいのかということを考えなければならないと思っています。
そういう中で、今後、ACPというものを充実させていくという話が出ているわけですが、医療の現場でそれをいかに充実させることができるか。大方の医師には望ましいと言って頂けるとは思うのですけれど、もっと重要なことが他にあるのかどうかもぜひ聞いてみたいと思っています。
横倉 大内先生も多くの終末期の患者さんとお話をされてきたと思うのですが、いかがですか。
大内 医学部の学生の時に、患者さんの死は敗北だと習ったのですが、よく考えますと、必ず人は亡くなるわけですから、医師の仕事は100%敗北ということになってしまいます。
そうした時に、それではどのように亡くなっていくか、ご本人にとってより良い亡くなり方をお手伝いするのも、やはり医師の役目だというように考え方を変えました。
それで、樋口先生にもご協力頂き、日本老年医学会が中心となり、『高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン』をつくりました。
書籍『死すべき定め』に出てくる医師のように、とにかく患者さんを生かそうと思って手をつくしたことが、かえって患者さんにマイナスになっている場合も起こり得る。それは、やはり患者さんの死が敗北であるという思想に立脚しているからだと思うのです。
その時に、少し発想を変えて、患者さんにとって良い亡くなり方がどうであるのかを考え、それを手伝うのも医師の役割だというように考えれば、素直に解釈できます。もちろん、それには終末期の判定やその方法など、いろいろな前提条件がありますが、それが私達の出したガイドラインの社会的な意義だったと考えています。
実際に、ガイドラインを出した後で、日本老年医学会の会員にアンケート調査をしたのですが、患者さんに終末期のことを説明しやすくなったとしています。ただ、法的な懸念が100%解決されたわけではないという回答も多数ありました。
横倉 終末期医療に関する法的な課題というのは、まだいくつか残っているかも知れませんが、樋口先生、その点についてはいかがですか。
樋口 法というのは、いい道具だと思いますが、使いこなすことが難しい道具であるとも言えます。法治国家であっても、適切な介入が必要な場合と、そうでない場合とがありますし、法律だけで人生が決まることはないのに、多くの人々が法を恐れ過ぎていることが、困ったところです。
横倉 ガイドラインにのっとってやっていれば大丈夫だという安心感を我々医師がつくっていかなくてはいけないと思います。
大内 この20年間で、メディアの対応も随分変わったと思います。例えば、終末期に栄養剤の点滴をしないのは非倫理的だとか、そういう論調が長く続きました。
しかし、我々が終末期にはある治療をしない、あるいは中止する選択肢もあり、患者さん及び家族の方々とよく話し合って結論を出すと提言した時に、メディアの論調は好意的でした。これは、やはり国民の意識が変わってきていることが背景にあるのではないかと思っています。
横倉 日医では、かかりつけ医にできるだけ終末期にも関わってもらいたいということで、ACPのパンフレットをつくったりしていますが、ACPについてはどのように思われていますか。
大内 事前指示の問題ですよね。日本ではアメリカと違って、そのことに法的な根拠がない。従って、裁判の証拠にならないので、ぜひ、いつの時点の事前指示を採用するのかも含めて、法律家の方々に検討して頂きたいと思います。
横倉 そうですね、ぜひ、今後もお二人にはそのことも含めてご議論をお願いしたいと思います。
最後になりますけれども、日医の会員の先生方に期待される役割ということに関して、一言ずつお願いできますでしょうか?。
樋口 私が小さかった頃は、医師は「お医者様」と呼ばれていました。それが今では「患者様」ということになっている。
昔は医師が少なくて、「様」と呼んで当然のようにありがたいという感覚だったと思いますが、それが「患者様」に変わり、本当に良い関係なのかというと、やはりちょっと違うだろうと思います。
結局、みんな基本的には地域でそれぞれ生きている中で、医師を頼るというのは、高齢者に限らず当たり前のことです。昔は、医療事故で医師を訴えるなんて、聞いたこともなかったわけで、そういう訴えたり、訴えられたりというのは、やはり良い関係ではない。だから、そこでのコミュニケーション、関係性がうまくいくことが大事だと考えていますし、地域の医師には終末期を含め、人生の良き助言者として、引き続き、頑張って頂ければありがたいと思います。
大内 私は所属している港区医師会の先生方との交流が多いのですけれども、医師会の先生方の活動を拝見すると、地域住民の健康に責任を持って仕事をしておられると強く感じます。
病院の中にこもっていますと、地域のための医療という意識が希薄になりがちですが、医師会の先生方とはお互いに良い連携をして、コミュニティー、あるいは高齢者全体の生活を守る医療を提供していければと考えています。
横倉 ぜひ、お願いしたいと思います。大内先生、樋口先生、本日は貴重なお話をありがとうございました。
| 大内 尉義(おおうち やすよし) 国家公務員共済組合連合会虎の門病院院長/東京大学名誉教授 1949年岡山県生まれ。1973年東京大学医学部卒業。1976年同大第3内科入局。三井記念病院内科、東大第3内科助手を経て、1985年米国テネシー大学へ留学。1986年東大老年病学講師、1995年同教授。その後、東大附属病院副院長を経て、2013年現職。 専門は老年医学、循環器病学(特に動脈硬化、高血圧)。日本老年医学会名誉会員。 |
| 樋口 範雄(ひぐち のりお) 武蔵野大学法学部特任教授/東京大学名誉教授 1951年新潟県生まれ。1974年東京大学法学部Ⅰ類卒業後、同助手(専攻は英米法)。1978年学習院大学法学部専任講師、1979年同助教授。1981~83年国際文化会館社会科学フェローシップによりミシガン大学及びアリゾナ大学ロー・スクール留学。1986年学習院大法学部教授。1992年東大大学院法学政治学研究科教授。2017年現職。 |



