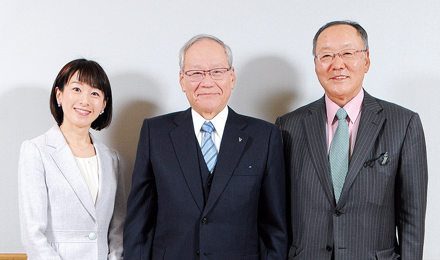
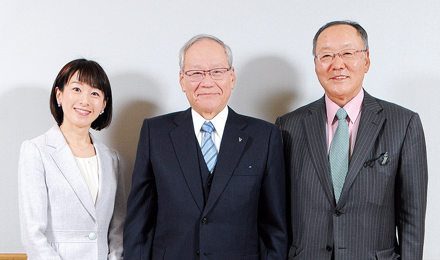
| 日医では、リビングウィルの国民への普及を目的として、横倉義武会長と岩尾總一郎日本尊厳死協会理事長との対談の模様を、3月26日付の読売新聞全国版の朝刊に掲載した(聞き手:フリーアナウンサー山本舞衣子氏)。今号ではその詳細をご紹介する。 |
|---|
山本 私が初めて、リビングウィルという言葉を知ったのは、東海大学安楽死事件の判決が出た1995年でした。その時にはまだ高校生で、進路を考える時期だったのですが、人がどうやって死を迎えるかということを、青春期ながらにすごく身に染みて感じた事件でした。
あれから20年以上が経ちますが、このリビングウィルという言葉は、今に至っても、皆さんが知っているものにはなっていないとの思いがあります。
今回は広く国民の皆さんにリビングウィルについて知ってもらうため、日医の横倉義武会長と日本尊厳死協会の岩尾總一郎理事長にお話を伺わせて頂くこととしました。どうぞよろしくお願いします。
まず、岩尾理事長にお聞きしたいのですが、超高齢社会の到来であったり、寿命の伸長などから、国民の終末期医療に関する意識も変化してきています。
そのような中で、「より良い最期を迎えること」について、今私達も真剣に議論すべきなのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
岩尾 日本は世界一長寿になったのですが、人間は誰でも最期を迎えるわけです。最期をどうするかという時に、従来は何でも医師にお任せするということがありました。治ればいいのですが、もう寿命が近くなってきた時には自然の摂理ですから、医師でも助けることはできません。そういう時に、自分はどういう形で最期を迎えるか。それは逆に言うと、どうやって自分がきちんとしたというか、納得できる余生を過ごせるかということと裏表の関係だと思うのですが、そういうことを自分で考えていく、自分で決めるというのが必要ではないかと思うのです。
私ども日本尊厳死協会は40年ほど前に設立されましたが、その頃に比べても新入会者は高齢者、特に超高齢の方々が増えてきています。そういう方々は自分の最期を自分で決める、自分の限られた生を充実して生きることにもつながります。従って、私達はこのような会員をサポートする活動をずっと続けているわけです。
山本 横倉会長は訪問診療もされていたということで、多くの方々の最期の場面に立ち会われてきたと思います。人が亡くなる時にはさまざまな形があると思いますが、今の日本の特徴として、どのような傾向があると思われますか。
横倉 生きとし生けるものは、全て終わりがあるということですね。それを日本の社会が、少し忘れているのではないかと思います。人がお亡くなりになるということは、残された者にとって非常につらいことなので、1日でも長く生きて欲しいという思いがあるわけです。
しかしながら、人間は、いつかは終末を迎えるわけですから、尊厳のある死ということ、人間らしく死にたいという思いも、一方で非常に強いと思います。
我々医師としては、そういう人間らしい終末というものを迎えて頂けるように、特に超高齢社会になってきますと、年間におよそ百数十万人の方がお亡くなりになる時代になりますから、そういう時にしっかり対応できるようにしたいと思っています。
山本 日本において死はタブーというか、あまり死の話をしてはいけないようなところが昔からあるかと思うのですが、もうそういう時代ではないですよね。
岩尾 そうですね。私が医学部を卒業したのは、もう40年以上も前になります。当時は救命救急については教わっていましたが、正直言って、看取りというようなことは授業にもなかったと思います。
けれども、平成22年からは医学部のカリキュラムの中で、終末期のことも取り入れられるようになりました。変わってきたのは、この10年あまりのことではないでしょうか。
山本 私も、15年前に看護学科を卒業した身なのですが、その頃は、生命倫理の授業はあまりなかったような気がしますね。
横倉 私は医師の仕事をしながら、地域の看護学校で倫理を教えていたのですが、その時には、「いわゆる消極的安楽死や積極的安楽死などの分類があって、日本で許されるのはどこまでか」「アメリカの事例では、人工呼吸器を止めるかどうかという話があるが、どう考えるか」というようなことについては、授業をした覚えがあります。
終末期医療を経済の視点から議論すべきではない
 山本 海外でも国によって、その捉え方は全然違うのでしょうね。
山本 海外でも国によって、その捉え方は全然違うのでしょうね。
そこで横倉会長に伺いたいのですが、一人ひとりが「最期の医療をどう受けたいか」を考えることが必要だというお話が先ほどありましたが、今の日医はどのようなスタンスをお取りになっているのですか。
横倉 日医では、これまで4回にわたって、会内の生命倫理懇談会で終末期医療の検討を行ってきました。人工呼吸器を取り外したことなどで医師が殺人罪で訴えられるというようなことがあったものですから、当初の議論では、消極的安楽死というか、人工呼吸をいつやめるかというような議論を行っていました。
そのような中で、昨年、経済財政諮問会議が取りまとめた「経済財政運営と改革の基本方針2016」で、「人生の最終段階における医療のあり方」ということが取り上げられたのですが、そういうものが、経済の視点から議論をされるということに対する懸念が、私どもにはありました。
人生の終末をどう迎えるかということは、人間としてのあり方を問うわけでありますから、単に経済や財政の話だけで済ませてはいけない、医療側でしっかり議論をしていく必要があると考え、今期の生命倫理懇談会では、特に高齢者の終末期のあり方を中心に哲学者や宗教家、法律家の方々を交えながら、「超高齢社会と終末期医療」について、議論して頂いています。
山本 高齢者ですと、自分で意思表示ができたりできなかったり、ケース・バイ・ケースだと思うのですが、実際に多くの会員を抱えておられる日本尊厳死協会では、どのような声を聞くことが多いですか。
岩尾 今、約12万人の会員がいるのですが、平均年齢が78歳で、かなり高齢となっています。5年ごとにデータを取っていますが、最近5年で入会してきた人の平均が72歳前後ですから、男性で10~11年、女性が14~15年、会員でおられることになります。
昨年亡くなられた会員の約92%に関しては、終末期医療について医師に自分の意思が受け入れられたという答えを頂いていますし、この割合は毎年9割以上ですので、私どもの尊厳死の意思表示カードは、だいぶ医師の方達にはご理解頂いているのかなと感じています。
ただ会員は約12万人、延べの人数で25万~26万人ですので、日本の国民全体からみると0・1%に過ぎず、かなり少ないわけです。アメリカでは25~40%のリビングウィルの保持率で、ドイツでは12%というデータもありますので、それと比較すると、もう少し国民に広げていく努力をしていかなければいけないと思っています。
山本 健康な時に、自分の死や家族の死のことって、実感がなかなかわかないですよね。
横倉 そうですね。身近でそういうことがあると、「あっ」と思うんですけどね。だから、自分で意識をした時に、そういったことを考える必要があると思いますね。
山本 QOL(生活の質)の次は、QOD(死の質)という話も伺いますが。
横倉 患者さんに対する医師の最後の仕事というのは、いかに最期を看取るのかということなのですね。
最期を看取る時に何を考えなければいけないかというと、いかに本人が望まれるような尊厳のある死というものを迎えてもらえるかということだろうと思います。
山本 やはりそれは、患者さんの残されたご家族の方も含めてということですか。
横倉 そうですね。家族の方に、ご両親なり、祖父母なりを本当に安らかに見送って頂く状況をつくっていくというのが大事だと思っています。
山本 患者さんが選択をされたとおりに看取ることができても、やはり残された者、遺族は、「これで良かったのかな」と思うところがあると思うのですが、その辺りの話し合いもしておく必要はありますか。
岩尾 現在、厚生労働省でも、医療関係職種の方々を対象に、終末期をどう看取るか、また家族にどのように説明すべきか、というような講習会を行っていると聞いています。
全国でも実施されているかと思いますけれども、終末期の看取りは、医師一人、あるいは看護師一人でやるべきものではなくて、チーム医療として、患者さんのみならず、ご家族にもきちんと説明し、特にグリーフケアが重要ですね。残された家族が納得できるように、ご本人の望まれた旅立ちだったということを分かってもらえるような技量というのは、医療関係者には必要なのではないかと思います。
山本 先ほど、横倉会長は、哲学者などの倫理系の方々も交えて議論をされているとおっしゃっていましたが、そういう面では通常の診療とは少し違うということですか。
横倉 そうですね。やはり見送るという心の持ち方が終末期医療には非常に重要になりますね。
ACPによる意思決定支援と「かかりつけ医」の役割
 山本 ところで、患者さんと家族、医療従事者を含めた、包括的なプロセスを重視した終末期の計画手法(Advance Care Planning:以下、ACP)が用いられるようになってきたと伺いましたが、これはどういうものなのですか。
山本 ところで、患者さんと家族、医療従事者を含めた、包括的なプロセスを重視した終末期の計画手法(Advance Care Planning:以下、ACP)が用いられるようになってきたと伺いましたが、これはどういうものなのですか。
岩尾 先ほど横倉会長もおっしゃったように、我々は「元気な時からリビングウィルを持っていて下さい」と言っているわけですが、いざご本人が病院に行く、あるいは医療機関にかかった時には、治療という行為があります。万一、治療に効果がなく、最期をどのようにしたいかという時に、単に医療のみならず、家族との関係、あるいは自分の最期をどうやって過ごしたいかというようなことを全てひっくるめて考えていこうというのがACPです。
最近、多くの病院ではこの取り組みを進めていると思いますが、今の流れは、家族の意向、あるいはご本人の意向、そして医療機関との間で合意を得た上で最期を過ごせるという形になってきていると思います。
ただ、まだ健康な方に、例えば「最期に輸液をしますか」とか、「胃ろうをつくりますか」あるいは「人工呼吸器を付けますか」ということを聞いても実感がわかないと思います。
病気になった時点で何が必要で、何が要らないのかということは、まさにACPの中で考えていくべき問題なのではないでしょうか。
山本 実際に日本尊厳死協会が発行している『世界のリビングウィル』を拝見したのですが、かなり詳細に項目があるんですね。
岩尾 そうですね。諸外国でも、この部分のページが非常に多くなっています。私どもは、なるべく皆さん方が持ちやすいように、包括的なものとして書きましたけれども、現実には現場の医師の方々からは、「これでも、いざという時に不十分ではないか」というご指摘を受けることもあります。
従って、私どもの尊厳死の意思表示カードに加えて、いざという時には各病院のACPと合わせてやっていくといった方法もいいと思います。これから先、会員向けのサービスとして、今はインターネットでいろいろと書類もつくれる時代ですから、そのような形でより細かいものを登録できるような仕組みもつくっていきたいと思っています。
山本 自分で書けなくなったり、意思表示ができなくなってしまった時のために、元気なうちから、ある程度話をしておくというのも大事かも知れませんね。
岩尾 大事ですね。認知症の方、あるいは脳卒中の後遺症などで言葉がなかなか出せないような方々ですね。そういうケースでは、自分の意思をどうやって伝えるかということが必要なわけです。
イギリス、フランス、ドイツなどの欧米諸国では、とりあえず以前に書いたリビングウィルがあれば、それを認めましょうということになっていますし、最近では台湾、それから韓国は2018年から法律が施行されますが、そのような意思表示を事前にしていれば、それは認めますということになります。
しかし、リビングウィルがない場合に、本人の最善の利益を守る人を事前に決めておく必要があります。医療における代理人ということになりますが、このような制度は、日本にまだ定着していないので、今後考えていく必要があると思います。
横倉 今、医療における代理人の話がありましたが、日医では今、国民の皆さんに「かかりつけ医を持ちましょう」という呼び掛けをしています。
日頃の診療の中で、患者さんもだんだんと高齢になってくるわけですから、「終末期はどうしますか」というような話も、かかりつけ医にして頂いて、そういう中でリビングウィルについても話をして頂くことが、私は非常に大事だと思いますね。
やはり残された家族には、「あの時、ああすれば良かった」という思いが必ず起こるわけですよ。その時に、かかりつけ医が「お母さんはこういうことをして欲しいと言っていましたよ」と伝えることによって、残された家族の方も非常に心安らかになるというようなことがよくありますので。
山本 家族だと、逆に遠慮してしまって、深い話ができないという高齢者の方も多いですからね。
横倉 そうですね。
山本 かかりつけ医の先生と長いお付き合いの中で、死生観についても話し合いができると、家族にとってもいいかも知れませんね。
横倉 そういった意味においても、かかりつけ医が非常に大事になってくると思うのです。
山本 巷では健康寿命、健康余命という話をよく聞きますが、その先の話をしていくことも大事ですね。
横倉 そうですね。また、今言われた健康寿命を延ばしていくためにも、かかりつけ医の役割が非常に大きいと考えています。どうすれば健康な老後を送れるかという指導も、できるだけ、かかりつけ医にして欲しいと思っています。
山本 納得いく最期を迎えられた患者さんと、残念ながらそうでない患者さんとでは違うものですか。
横倉 違いますね。極端な場合、その家族の行き場のない気持ちというのが、周辺の医療者にぶつけられるというようなこともありました。
穏やかな終末を迎えるために
 山本 どうにもしようがないことではありますけれどね。
山本 どうにもしようがないことではありますけれどね。
では、今後、日医として、このリビングウィル、終末期医療に対して、どのような取り組みを考えていらっしゃいますか。
横倉 多くの国民の皆さんに、できるだけリビングウィルを持ってもらうということを進めていきたいと思っています。
また、かかりつけ医の先生方には、患者さんがだんだん高齢になって弱ってきた時に、リビングウィルをどう残したらいいのか質問をされた場合に、きちんと答えられるようにしていきたいと思っています。
山本 日本尊厳死協会が作成しているリビングウィルの「尊厳死の宣言書」は、どうしたら入手できるのですか。
岩尾 私どもの協会に請求頂ければ、申込書をお送り致しますので、お問い合わせ頂ければと思います。
横倉 ホームページからもダウンロードできるのですよね。
岩尾 はい。
山本 それは便利ですね。
岩尾 横倉会長がおっしゃったように、これだけ高齢の方々が増えてきて、お亡くなりになる方が増えてきますと、最期をどこで迎えるのか、病院の数も限られている、施設の数も限られるとなると、自宅でという話が多くなる。そうなると、かかりつけ医の先生が訪問看護ステーション等と連携をとりながら、その人が住み慣れた環境の中で最期を看取ってあげるというのが、一番自然なのだと思います。
山本 そうですよね。
岩尾 かかりつけ医もだいぶ普及してきていますし、看取って頂く先生の数も随分増えてきたと思うので、私どもとしては何かあったら救急車を呼ぶのではなく、かかりつけ医の先生に連絡をするということの方がいいと思っています。
救急車を呼ぶと、彼らは救命救急をするのが仕事ですから、ご本人が静かに最期をと思っていても、そこにご本人の意思との乖離(かいり)が出てくる。
昔から診てもらっている、あるいはそこの地域で診てもらっているかかりつけ医の先生に連絡すれば、これはもう症状としては死に至るプロセスなんだと。そういう時であれば、この程度の治療ではないかということが、かかりつけ医だったら分かるということだと思います。
山本 そうですね。超高齢社会を迎え、医療界は問題が山積みだと思うのですが、最後に、横倉会長から国民の皆さんに向けてメッセージを頂けますでしょうか。
横倉 終末期に関しては、健康な時にはあまり考えないものですが、いつかは自分の生命が終わる時がくる。その生命が終わる時に、どうか穏やかな終末を迎えたいという希望が多いと思うのですね。そのためには、しっかり自分の意思を残しておくことが大事だと思います。
山本 そして生命倫理に関して、若いうちからの教育も本当に重要ですよね。
横倉 そうですね。
山本 この記事が皆さんで終末期医療のことを考えるきっかけになるといいですね。
今日はどうもありがとうございました。
横倉 ありがとうございました。
岩尾 ありがとうございました。
|
岩尾 總一郎(いわお そういちろう)
日本尊厳死協会理事長 1973年慶應義塾大学医学部卒業。同大学院にて医学博士号取得後、テキサス大学留学。産業医科大学助教授を経て、1985年厚生省入省。 2003年厚生労働省医政局長に就任し、2005年に退官。その後世界保健機関(WHO)健康開発センター所長などを歴任し、2012年6月から現職。 |
| キーワード:リビングウィルとは |
|---|
| 生前の意思のことで、病気などで意思表示ができなくなった時に備え、延命治療などの希望をあらかじめ残しておくこと。「事前指示書」とも呼ぶ。 |



