令和7年(2025年)4月20日(日) / 日医ニュース
医療機関の経営状況への対応等、直近の課題に関する19の質問に回答 新理事には加納大阪府医師会長を選任
第158回日本医師会臨時代議員会
- 000
- 印刷


| 第158回日本医師会臨時代議員会が3月30日、日本医師会館大講堂で開催された。 当日は松本吉郎会長のあいさつの後、角田徹副会長から令和7年度日本医師会事業計画及び予算について報告した他、代議員からの19の質問に対して、執行部から回答を行った。 また、「第1号議案 日本医師会理事選任の件」については立候補者が今回の定数どおり1名であったため、加納康至代議員(大阪府医師会長)が挙手多数により選任された。 |
|---|
冒頭あいさつを行った松本会長は、(1)医療機関経営の危機的状況の改善に向けて、(2)組織強化、(3)新たな地域医療構想等の医療法改正、(4)医師偏在対策、(5)かかりつけ医機能が発揮される制度整備、(6)医療DX、(7)医薬品をめぐる最近の状況、(8)7月の参議院選挙―等について言及した。
(1)では、「著しく逼迫(ひっぱく)した経営状況を鑑みると、まずは補助金での早期の適切な対応が必要であり、更に診療報酬で安定的に財源を確保しなければならない」と指摘。令和8年度診療報酬改定の前に、期中改定も視野に入れて、補助金と診療報酬の両面からの対応を求めていくとした。
また、「骨太の方針2025」の取りまとめに向けて、「『高齢化の伸びの範囲内に抑制する』という社会保障予算の目安対応の廃止」「診療報酬等について、賃金・物価の上昇に応じて適切に対応する新たな仕組みの導入」「小児医療・周産期体制の強力な方策の検討」の三つの対応が必要との考えを示した。
(2)では、組織強化への協力に感謝の意を示した上で、組織強化の一環として、新たに構築した医師会会員情報システム「MAMIS」を紹介。「医師会の組織強化の眼目は、現場に根差した提言をしっかりと医療政策の決定プロセスに反映させていく中で、医師の診療・生活を支援し、国民の生命と健康を守ることにある」とし、対外的にも医師会のプレゼンスを一段と高められるよう、引き続き努めていくとした。
(3)では、新たな地域医療構想の議論に当たっては、地域医療構想に介護を含めること、現行の「回復期機能」を「包括期機能」とすることを提案し、実現したこと等を報告した。
(4)では、昨年12月25日に厚生労働省から公表された「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」について、基本的には評価できるとの考えを改めて説明。日本医師会として、中堅・シニア世代の医師に対する、総合的な診療能力などのリカレント教育にも取り組んでいくとした他、総合パッケージに記載のある「全国的なマッチング機能の支援」に関しては、日本医師会女性医師支援センターが応札に向け対応していることを明らかにした。
(5)では、「かかりつけ医機能報告制度には多くの医療機関に手を挙げて参画して欲しい」とするとともに、日本医師会としても「かかりつけ医機能報告制度にかかる研修」を新設することを報告した。
(6)では、「国民・患者の皆様への安全・安心でより良い医療の提供と、医療現場の負担軽減に資するものでなければならない」という医療DXに関する日本医師会の考えを改めて説明。今後も、医療機関の業務負担、費用負担を減らすための医療DXとなるよう尽力していくとした。
(7)では、医療現場では依然として医薬品供給不安が続いていることを憂慮。更なる実効性の向上や迅速な対応が求められるとして、補助金等の十分な予算措置も含め、現場の声を踏まえた意見・要望をしっかりと国に伝えていくとした。
また、昨今、社会保険料を下げることを目的としてOTC類似薬の保険適用除外を求める動きが見受けられることにも触れ、強い懸念を示した。
(8)では、7月の参議院選挙は「医療の未来を左右する重要な選挙である」として、釜萢敏副会長に対する絶大な支援を求めた。
その他、松本会長は財政健全化の立場から「"大きなリスクは共助、小さなリスクは自助"との主張も一部にあるが、日本医師会はそれには反対である」と主張。その上で、国民生活を支える基盤として、「必要かつ適切な医療は保険診療により確保する」という国民皆保険制度の理念を今後とも堅持すべきであり、給付範囲を縮小すべきではないとの考えを改めて強調した。
また、政府に対して、「高齢化の伸び等により財政が厳しいことも承知しているが、安全性や公平性を損なわないよう、慎重な議論とバランスの取れた政策を求めていきたい」と述べた。
会長あいさつ全文
https://www.med.or.jp/nichiionline/article/012174.html
理事
 |
加納 康至(かのう やすし)71歳・大阪 大阪府出身、神戸大卒、大阪市北区医理事、大阪府医理事・副会長を経て、令和7年より大阪府医会長。内・循環器科 |
代表質問に対する執行部からの回答要旨
1 病院と診療所の分断を図る動きについて
 案浦美雪代議員(福岡県)からの、財務省による病院と診療所の分断を図る動きに関して日本医師会の見解を問う質問には、角田徹副会長が回答した。
案浦美雪代議員(福岡県)からの、財務省による病院と診療所の分断を図る動きに関して日本医師会の見解を問う質問には、角田徹副会長が回答した。
同副会長はまず、国民の生命と健康を守るためにも、病院と診療所の結束は欠かせず、日本医師会は病院団体との連携を緊密に重ねてきたとした。
更に、四病院団体協議会などとの定期的な協議の場を設けていることや6病院団体と共に会見を行い、合同声明を公表したこと等を説明。その上で、財務省等の財政的な見地からの動きに対して、これまでもその都度、強固な連携の下に対応してきたが、恣意(しい)的な分断工作に対しては、今後も医療界全体として状況を正確に把握し情報共有することが、一致団結して取り組むためには極めて重要になると指摘し、「そのための情報発信や対話を続けていく」とした。
また、医療界が一体・一丸となって取り組みを進めていくためにも、引き続き病院団体との緊密な連携を更に深めていく考えを示した。
2 かかりつけ医機能報告制度について
 三浦一樹代議員(兵庫県)からの、かかりつけ医機能報告制度に関する(1)フリーアクセスを阻害させる管理医療への懸念、(2)オンライン診療の適正な活用や協議の場での議論、(3)2号機能報告の数量的な評価―についての質問には、城守国斗常任理事が回答した。
三浦一樹代議員(兵庫県)からの、かかりつけ医機能報告制度に関する(1)フリーアクセスを阻害させる管理医療への懸念、(2)オンライン診療の適正な活用や協議の場での議論、(3)2号機能報告の数量的な評価―についての質問には、城守国斗常任理事が回答した。
同常任理事は(1)について、フリーアクセスの阻害につながる制度化には明確に反対してきた結果、その考えに沿う形で本制度が令和7年4月より施行されることになったと説明。一方で、かかりつけ医の制度化に向けた主張が今後も財務省等により展開される懸念は十分にあると指摘し、フリーアクセスを守るべく今後も主張を重ねていく意向を示した。
(2)に関しては、今国会に法案が提出されていることに触れ、法制化によりオンライン診療が適切に進められるよう引き続き尽力していく姿勢を示した。また、「協議の場では、地域医師会の積極的な参画、リーダーシップが極めて重要であり、都道府県医師会においても好事例の情報共有等、精力的な支援をお願いしたい」と述べた。
また、(3)については、「現時点では数量的な評価につながる恐れはない」とした上で、本報告制度が医療費削減や医療提供体制の改悪を招く手段として利用されないよう、今後とも鋭意主張していくとした。
3 次期診療報酬改定(来年)に望むことは新設された生活習慣病管理料(Ⅱ)とリフィル処方の廃止である
 小沼一郎代議員(栃木県)からの、生活習慣病管理料(Ⅱ)とリフィル処方の廃止を求める意見に対しては、城守常任理事が、「リフィル処方箋は令和4年度改定、生活習慣病管理料(Ⅱ)は令和6年度改定において、厳しい議論の結果、いずれも大臣折衝で最終決定された忸怩(じくじ)たる思いのある項目である」と回答。
小沼一郎代議員(栃木県)からの、生活習慣病管理料(Ⅱ)とリフィル処方の廃止を求める意見に対しては、城守常任理事が、「リフィル処方箋は令和4年度改定、生活習慣病管理料(Ⅱ)は令和6年度改定において、厳しい議論の結果、いずれも大臣折衝で最終決定された忸怩(じくじ)たる思いのある項目である」と回答。
財務省は社会保障関係予算の削減の中で、特に外来医療費の削減を企図しているとし、「社会保障関係費を、高齢化による増加分に相当する伸びに収めるという、いわゆる『目安対応』が『骨太の方針2021』に書き込まれ、この考え方が現在も踏襲されていることが根本原因である」と説明した。
その上で、生活習慣病管理料(Ⅱ)とリフィル処方箋(せん)を無くせば、今後、別の医療費項目を対象とした医療費削減が行われかねないことを強調。令和8年度診療報酬改定に向けて「骨太の方針2025」の議論が本格化する中で、「目安対応」の廃止に向け、全力で政府・与党に要望していく考えを示し、代議員に対して協力を求めた。
4 医師の働き方改革による地域医療への影響等について
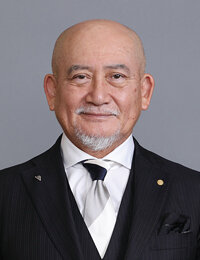 中島均代議員(鹿児島県)からの、医師の働き方改革による地域の医療提供体制への影響についての質問には、濵口欣也常任理事が回答した。
中島均代議員(鹿児島県)からの、医師の働き方改革による地域の医療提供体制への影響についての質問には、濵口欣也常任理事が回答した。
同常任理事は「昨年4月の制度開始前後の調査では、各医療機関が想定していたほど地域医療への影響は大きくなかった」とする一方、今後どのように変化していくかを確認するため、調査を継続する意向を説明。地域の具体的な医療事情をタイムリーに把握できる都道府県並びに郡市区等医師会からの情報提供を要請した。
開業医(病医院の管理者を含む)へのサポートについては、相談窓口として、まずは都道府県の医療勤務環境改善支援センターの活用を求めた。
また、医療機関勤務環境評価センター(以下、評価センター)の動きについては、今年の秋から指定更新の評価が受審できる体制を準備していることを説明。サーベイヤーの委嘱期間が今年10月末で満了となることから、次期の医療サーベイヤー推薦に協力を求めた他、医師の働き方改革に関する情報は適宜、評価センターのホームページ等を通じて医療機関に提供していく考えを示した。
5 医療DXに関する現状と将来に対する不安について
 友岡俊夫代議員(奈良県)は、高齢会員が電子カルテ導入や補助金申請などを行う際の支援を求めるとともに、電子カルテ情報共有サービスや将来発生する保守管理費用に関する医療機関への補助を国に求めるよう要望。長島公之常任理事は高齢会員への支援について、オンライン資格確認の導入のための補助金申請が日本医師会の申し入れにより、紙申請の受け付けも可能になったことなどを説明し、今後も国に対して、種々の手続きの簡略化や相談窓口の設置を求めるとともに、電子カルテに慣れてもらうための支援も行っていく考えを示した。
友岡俊夫代議員(奈良県)は、高齢会員が電子カルテ導入や補助金申請などを行う際の支援を求めるとともに、電子カルテ情報共有サービスや将来発生する保守管理費用に関する医療機関への補助を国に求めるよう要望。長島公之常任理事は高齢会員への支援について、オンライン資格確認の導入のための補助金申請が日本医師会の申し入れにより、紙申請の受け付けも可能になったことなどを説明し、今後も国に対して、種々の手続きの簡略化や相談窓口の設置を求めるとともに、電子カルテに慣れてもらうための支援も行っていく考えを示した。
また、国への要望に関しては、補助金の補助率や上限額を現実的な額に引き上げるとともに、実態に即した対応を求めていくとした。
その上で、同常任理事は引き続き医療機関の費用負担と業務負担を極力減らすなど、医療DXの将来への不安解消に向けた取り組みを進めていく姿勢を示し、理解を求めた。
6 学校医不足を解消するために
 野中雅代議員(北海道)が、学校医不足問題の解決のため、学校医活動に勤務医がより取り組むことができる環境整備を求めたことに対して、渡辺弘司常任理事はその実現のために解決すべき課題として、(1)兼業の問題、(2)移動や健診に対する補償の問題―があると指摘。(1)に関しては、昨年から厚生労働省、文部科学省と協議を行っていることを明らかにするとともに、(2)については今後検討していく考えを示した。
野中雅代議員(北海道)が、学校医不足問題の解決のため、学校医活動に勤務医がより取り組むことができる環境整備を求めたことに対して、渡辺弘司常任理事はその実現のために解決すべき課題として、(1)兼業の問題、(2)移動や健診に対する補償の問題―があると指摘。(1)に関しては、昨年から厚生労働省、文部科学省と協議を行っていることを明らかにするとともに、(2)については今後検討していく考えを示した。
更に、同常任理事は「学校医の環境整備という点では、学校保健安全法施行規則に定められている健診項目の再検討や、機器を用いた検診の導入、健診日程の見直しなどもその方策の一つであり、学校保健委員会で検討している」とした他、「勤務医の兼業に道が開けたとしても、学校医活動を始めとした、医師会のかかりつけ医活動のどの部分を担ってもらうのか」という問題もあると説明。「容易に解決できる課題ではないが、非常に重要な問題と認識しており、継続して対処していく」とした。
7 医師の働き方改革の影響や医師偏在対策等についての現場の勤務医、特に若手医師たちの意見を拾い上げるシステムの構築について
 若林久男代議員(香川県)が医師の働き方改革や医師の偏在対策等について、現場の勤務医、特に若手医師達の意見を拾い上げるシステムの構築を求めたことに対して、今村英仁常任理事が回答を行った。
若林久男代議員(香川県)が医師の働き方改革や医師の偏在対策等について、現場の勤務医、特に若手医師達の意見を拾い上げるシステムの構築を求めたことに対して、今村英仁常任理事が回答を行った。
同常任理事は勤務医委員会と病院委員会の合同開催を新たに試みる他、全国医師会勤務医部会連絡協議会、都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会といった既存の取り組み以外にも、組織強化の一環として、日本医師会の役員が各地を訪問し、勤務医の声を直接聞く機会を増やすよう努めていることなどを説明。
更に、勤務医の声が確実に日本医師会にまで届いていると実感し、日本医師会の存在をより身近に感じてもらうことも極めて重要であると指摘。その実現のため、既存の広報手段の更なる活用の検討に加えて、シンポジウム「未来ビジョン"若手医師の挑戦"」などを通じ、医師会活動に対する臨床研修医や若手勤務医の理解醸成にも努めるなど、あらゆる機会を活用して勤務医の意見にしっかり耳を傾けていくとして、理解と協力を求めた。
8 日本医師会は認知症施策に対してもっと積極的に取り組むべきである
 丸木雄一代議員(埼玉県)からの、(1)認知症共生街づくり、(2)産業医へのレカネマブ・ドナネマブの使用啓発、(3)認知症疾患医療センターの再編―に関する日本医師会の見解を問う質問には、江澤和彦常任理事が回答。
丸木雄一代議員(埼玉県)からの、(1)認知症共生街づくり、(2)産業医へのレカネマブ・ドナネマブの使用啓発、(3)認知症疾患医療センターの再編―に関する日本医師会の見解を問う質問には、江澤和彦常任理事が回答。
(1)についてはかかりつけ医の果たす役割が重要であること、「通いの場」としての取り組みを医療機関等で開催することを提案していることを説明した上で、引き続き、厚労省担当部局を始め、関係者と連携して、その実現に向け尽力していく考えを示した。
(2)に関しては、抗アミロイドβ抗体薬の留意点を説明した上で、「産業医が主治医や事業所と連携して就業上の必要な措置を講じていくためにも、本治療の情報把握は有用であり、日本医師会認定産業医の研修会等を通じて的確に発信できるよう随時検討していく」とした。
また、(3)については同センターが期待される役割を担うためには、実績報告の見える化や新規・更新の認定を行う都道府県の協議会の役割も重要になると指摘。「日本医師会としても同センターの質の向上に向け、これまで同様、引き続き厚労省担当部局等と協議していく」と述べた。
9 高齢者施設・住宅等での訪問看護における請求の適正化に関する取組について
 荘司輝昭代議員(東京都)は、訪問看護事業所、高齢者住宅・施設等の報酬請求に関して審査体制の強化等を求めるとともに、不正請求を行う事業所へ指示書を交付する医師への教育・指導に関する取り組みについて質問した。
荘司輝昭代議員(東京都)は、訪問看護事業所、高齢者住宅・施設等の報酬請求に関して審査体制の強化等を求めるとともに、不正請求を行う事業所へ指示書を交付する医師への教育・指導に関する取り組みについて質問した。
佐原博之常任理事は訪問看護ステーションへの新たな指導の仕組みが設けられることを説明した上で、「高額な請求をする事業所が一律に不正を行っているということではないが、どのようなサービス提供を行っているのかを個別指導で確認し、仮に不適切であれば正していくことが必要だ」と指摘。診療報酬で対応すべきことについては、次回改定に向けて中医協で検討していくとした。
また、高齢者施設や高齢者住宅等の適正な運営については、これまでも厚労省にその対応を強く求めてきたが、有料老人ホームにおける課題等を議論するために新たに設置される検討会においても、引き続きその対応を協議していくとした。
更に医師への教育・指導に関しては、新たに導入される高額レセプトの指導や教育的指導による実態の把握・分析を踏まえ、指示を出す医師に対する適切なサービス提供のあり方の周知・啓発を行うよう、国に対して働き掛けていく考えを示した。
10 新たな感染症拡大時における、日本医師会の立ち位置について
 禹満代議員(京都府)からの、新たな感染症拡大時の国に対する日本医師会の立ち位置を問う質問には、釜萢敏副会長が回答した。
禹満代議員(京都府)からの、新たな感染症拡大時の国に対する日本医師会の立ち位置を問う質問には、釜萢敏副会長が回答した。
同副会長は、新型コロナウイルス感染症まん延時の状況を振り返った上で、今後は政府の指揮系統が「内閣感染症危機管理統括庁」並びに「国立健康危機管理研究機構」によって取りまとめられることになると説明。日本医師会としても協力要請に応じて、新たな会議体に参画し、意見を述べていく意向を示した。
その上で、日本医師会が参画している平時における国の審議会等の発言を通じて、審議会の他の構成員や担当省庁の信頼を得ておくことが極めて重要であると強調した。
また、同副会長は今後について、「引き続き色々な手段を駆使し、直接国民に必要な情報をタイムリーに届けるばかりでなく、さまざまなレベルで政府や国会議員に、医療現場からの声を速やかに伝え、政策判断に生かされるように、全力で取り組んでいく」と述べるとともに、医師会並びに会員の先生方が心置きなく感染症危機管理対応に協力してもらえるよう尽力していくとして、理解と協力を求めた。
11 医師会立准看護師・看護師養成所存続の危機
 医師会立准看護師・看護師養成所存続のための手段の一つとして、日本医師会の医療関係者検討委員会が提案した「養成所のサテライト構想」に関して、その運営に行政が参画しやすいモデルの公表などを求める森俊明代議員(徳島県)の要望には、黒瀬巌常任理事が回答した。
医師会立准看護師・看護師養成所存続のための手段の一つとして、日本医師会の医療関係者検討委員会が提案した「養成所のサテライト構想」に関して、その運営に行政が参画しやすいモデルの公表などを求める森俊明代議員(徳島県)の要望には、黒瀬巌常任理事が回答した。
同常任理事は、サテライト構想の主旨は学生の地元定着と養成所の人的・経済的な負担軽減の両立にあることなどを概説した上で、「厚労省からは人員や設備などの必要条件を満たせば、本方式の実現は可能との回答を得ている」とする一方で、サテライト化した場合に1校分として扱われてしまうという大きな障壁もあることなどを説明。医療は地域住民にとって生活基盤であり、人的流入の少ない地域で看護職を安定確保するためには、自治体にも地域に根差した養成所の存在が極めて大きいことを認識し、運営を後押ししてもらう必要があるとした。
今後については、協働可能なモデルの検討を行政と行うとともに、引き続き厚労省等関係省庁、地方自治体や関連団体に対して、丁寧かつ強力に支援を要請していく意向を示した。
12 今後想定される医療のサイバーセキュリティ問題は?
 目々澤肇代議員(東京都)は、現行の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」が見直される際に、「マルウェア感染の増加」「医療機関のICTシステムへの侵入等への対策」などを盛り込むよう求めるとともに、オンライン診療に使う機材と院内の電子カルテ等のネットワークとの分離について、その定義の明確化を要望した。
目々澤肇代議員(東京都)は、現行の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」が見直される際に、「マルウェア感染の増加」「医療機関のICTシステムへの侵入等への対策」などを盛り込むよう求めるとともに、オンライン診療に使う機材と院内の電子カルテ等のネットワークとの分離について、その定義の明確化を要望した。
これに対して、長島常任理事は、ガイドラインの改定について作業は始まっていないものの、改定作業班には日医総研から専門家が参画していることを説明し、検討の際には今回の指摘事項への対応を働き掛けていくとした。
また、定義の明確化を求める要望に対しては、厚労省の指針が改訂され、セキュリティ対策の記載についても充実が図られていることから、今回の指摘を踏まえて、早速、日本医師会ホームページのメンバーズルーム内の「オンライン診療について」のページに、厚労省の指針から該当する対策を整理して掲載し、都道府県医師会宛に周知を図ったことを報告。今後、国において指針の改定等が行われる際には、今回の指摘のリスクについても対応するよう要請していくとした。
13 持続可能な医療を提供するための税制改革の提言
 大原正範代議員(北海道)は、持続可能な医療を提供する方策として、(1)医療機器、医療材料、医薬品、委託費に掛かる消費税免税、(2)へき地勤務の医師の所得税減税、必要だが希望者が減少している診療科で専門医を維持している期間の所得税減税―を提案。政府に提言することを求めたことに対しては、宮川政昭常任理事が答弁を行った。
大原正範代議員(北海道)は、持続可能な医療を提供する方策として、(1)医療機器、医療材料、医薬品、委託費に掛かる消費税免税、(2)へき地勤務の医師の所得税減税、必要だが希望者が減少している診療科で専門医を維持している期間の所得税減税―を提案。政府に提言することを求めたことに対しては、宮川政昭常任理事が答弁を行った。
同常任理事は、(1)について既に会内の医業税制検討委員会で医療機関の仕入段階の消費税負担に着目し、その一部を免税とする仕組みの検討を開始しており、更に検討を進めていく考えを表明。(2)に関しては、「医師偏在対策を支援する新たな税制措置の創設については、会内の医業税制検討委員会で検討していたところであるが、へき地に勤務する医師など偏在解消に協力的な病院勤務医に対する減税措置は重要な観点であることから、医師偏在対策に資する税制要望として、引き続き検討していく」とした。
14 ARIサーベイランスに係る定点医療機関の負担と一部ワクチンの定期接種化について
 河野幸治代議員(大分県)からの、急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスに係る定点医療機関の負担軽減等と、小児のインフルエンザ及びおたふくのワクチン、妊婦のRSワクチンの定期接種化に関する要望には、笹本洋一常任理事が回答した。
河野幸治代議員(大分県)からの、急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスに係る定点医療機関の負担軽減等と、小児のインフルエンザ及びおたふくのワクチン、妊婦のRSワクチンの定期接種化に関する要望には、笹本洋一常任理事が回答した。
同常任理事は、「重篤な被害をもたらす新興感染症の多くは、呼吸器症状を呈することから、ARIの立ち上がり等をデータとして把握することが必要」と指摘。定点医療機関の負担増への懸念には、報告様式が改定され、集計が単独の項目かつ5歳刻みの簡易様式とされたことを説明し、理解を求めた。
また、定点数を減らす方針に関しては、「減少・統合によってデータの信頼性は失われないとの説明を受けている」と述べ、今後の状況を注視していく姿勢を示した。
定期接種ワクチンの追加については、「重要性を認識している」とした上で、定期接種化は、メリット・デメリット等の科学的なエビデンスを積み上げ、優先度を考慮して総合的に判断されることなどを説明。引き続き全ての国民にワクチンにより防止できる疾患が増えるよう、国に対して機を捉えて発言していくとした。
15 病院と有床診療所の差し迫った経営危機への対策について
 赤石隆代議員(宮城県)からの、病院と有床診療所の経営危機への対応を求める要望には、茂松茂人副会長が回答した。
赤石隆代議員(宮城県)からの、病院と有床診療所の経営危機への対応を求める要望には、茂松茂人副会長が回答した。
同副会長は、まず、物価高騰などへの対応について、重点支援地方交付金や令和6年度補正予算による補助が実現していることを紹介。その上で、これらの補助だけでは物価高騰等には追い付いていないとの認識を示すとともに、自治体ごとの対応のばらつき等に関して改善を求めてきたことを説明した。
また、3月12日に6病院団体との合同声明を発表し、「まずは補助金による機動的な対応が必要だが、直近の賃金上昇と物価上昇を踏まえると、令和8年度診療報酬改定の前に期中改定での対応も必要である」と表明するなど、病院団体と歩調を合わせて対応していることを強調。6月に閣議決定される「骨太の方針2025」に、合同声明でも主張している、「『高齢化の伸びの範囲内に抑制する』という社会保障予算の目安対応の廃止」「診療報酬等について、賃金・物価の上昇に応じて適切に対応する新たな仕組みの導入」が盛り込まれることが極めて重要になるとした。
16 新たな地域医療構想の策定に向けた日本医師会の取り組みと諸問題について
 秋山欣丈代議員(静岡県)は新たな地域医療構想に関して、(1)地域の意見を反映するための取り組み、(2)持続可能な在宅医療の提供体制の確保、(3)地域医療介護総合確保基金の拡充や弾力的な運用―について、日本医師会の見解を求めた。
秋山欣丈代議員(静岡県)は新たな地域医療構想に関して、(1)地域の意見を反映するための取り組み、(2)持続可能な在宅医療の提供体制の確保、(3)地域医療介護総合確保基金の拡充や弾力的な運用―について、日本医師会の見解を求めた。
坂本泰三常任理事はまず、(1)について、新たな地域医療構想に関わる会内の委員会において担当役員が最新の情報を共有していることを説明するとともに、委員会委員に対して、各ブロックへの報告並びに意見の取りまとめを求めた。また、連絡協議会の開催等の活動を紹介し、今後も地域の意見をしっかりと受け止め、国に伝えていく姿勢を示した。
(2)では、「介護との連携無くして医療提供体制の議論は完結しない」との考えを強調。その上で、在宅医療の議論について、各地域の将来展望に応じて考える他、生活を支える介護サービスも併せて検討することが必要であると主張した。
(3)では、これまでの日本医師会の要請により、地域連携や再編統合の人材支援など、ソフト事業の補助も認められていることを説明し、理解を求めた。
17 学校管理下の文書の料金徴収の有無について
 橋爪英二代議員(山形県)からの、学校管理下における文書の料金徴収の有無の現況と、本件の根拠となる通知「学校安全会における医療関係事項について」(昭和35年5月20日 日医発第31号)に対する見解を問う質問には、松岡かおり常任理事が回答した。
橋爪英二代議員(山形県)からの、学校管理下における文書の料金徴収の有無の現況と、本件の根拠となる通知「学校安全会における医療関係事項について」(昭和35年5月20日 日医発第31号)に対する見解を問う質問には、松岡かおり常任理事が回答した。
同常任理事は、まず、本質問に該当する「災害共済給付制度の補償を受けるために必要な文書」について、現行の取り扱いとなった経緯を詳説。この料金を徴収すると、保護者と学校間のトラブルの発生やそれによる医療機関への影響が懸念されると指摘した。
また、料金徴収の有無の現況については、多くの医療関係職種で日本医師会の方針と同様の対応がなされていると報告。
本文書については「その取り扱いが学校や保護者にも定着しているものであり、改めて文書を発出するとなれば国レベルの大きな話になる」として、日本医師会が発出した当時の考えを尊重し、現状を維持して欲しいと要望した。
18 医業承継支援について
 鳥澤英紀代議員(岐阜県)は医業承継支援に関して、(1)医業承継支援事業等の都道府県医師会間の情報交換の機会の設定、(2)医業承継支援のトライアル事業の成果―について質問。
鳥澤英紀代議員(岐阜県)は医業承継支援に関して、(1)医業承継支援事業等の都道府県医師会間の情報交換の機会の設定、(2)医業承継支援のトライアル事業の成果―について質問。
藤原慶正常任理事は、(1)について、福島、秋田の両県医師会では、既に地域医療介護総合確保基金を活用した医業承継支援またはマッチング事業を行っていることや、本年1月からは山形県医師会でも承継事業が開始されたことを紹介した上で、地域の課題は多様であるが、先行事例が参考となることもあるとして、「情報共有の機会の設定、広域でマッチング情報を共有できる仕組みについて検討していく」と述べた。
(2)については、令和2年に日本医師会が民間事業者と「第三者医業承継のトライアル事業に関する包括連携協定」を結び、その一環として、秋田県医師会が民間事業者や金融機関と包括連携協定を締結したことを説明。事業承継セミナー等が実施されたが、仲介料が高額等の理由から、本協定に基づいた承継の事案はなかったことを報告した。
19 勤務医の職場環境改善と組織力向上に向けた取り組み
 原晃代議員(茨城県)からの、救急要請時の緊急性が認められない場合の選定療養費に対する日本医師会の見解並びに、勤務医の職場環境改善と組織力向上に向けた取り組みに関する質問には細川秀一常任理事が回答した。
原晃代議員(茨城県)からの、救急要請時の緊急性が認められない場合の選定療養費に対する日本医師会の見解並びに、勤務医の職場環境改善と組織力向上に向けた取り組みに関する質問には細川秀一常任理事が回答した。
同常任理事はまず、救急搬送時の選定療養費について、勤務医の処遇改善の一策となり得るとして、先行事例を参考に全国展開について国の検討会等で議論していく考えを示した。
勤務医の疲弊と環境改善に関しては、勤務医との直接的な対話に努める中で、その声を受け止め、さまざまな課題の解決に努めていくことが日本医師会の基本的な考え方であると説明。今後も病院委員会と勤務医委員会の合同委員会の開催など、新たな活動も通じて勤務環境の改善を図る他、MAMISの活用等の具体的な取り組みも加速させるとした。
その上で、勤務医の医師会入会のメリットは、医師賠償責任保険や医師年金等の会員サービスはもちろんのこと、更に重要なのは、「勤務医の声を汲み取り、中央に伝えられることである」と強調。「勤務医の声を一段と受け止め、医療界が一丸となって、より良い医療環境を実現していく」と述べ、引き続きの支援を求めた。



