
医師に求められる「緩和の視点」:細川 豊史先生
細川 豊史先生
日本緩和医療学会 理事長
京都府立医科大学附属病院 疼痛緩和医療部 部長
京都府立医科大学 疼痛・緩和医療学講座 病院教授
緩和ケアは終末期だけのものではない
 現代において、がんは非常に一般的な病気になっています。今やがん患者さん全体の5年生存率は60%以上であり、まだまだ働ける現役世代のがん患者さんも珍しくありません。このため、手術や抗がん剤治療、放射線治療の後に社会復帰するというケースも多くあります。男性の60%、女性の48%ががんになる時代ですから、医学生のみなさんも卒業して医師になったら、がんの患者さんを主治医として診ることになる場合も多いでしょう。
現代において、がんは非常に一般的な病気になっています。今やがん患者さん全体の5年生存率は60%以上であり、まだまだ働ける現役世代のがん患者さんも珍しくありません。このため、手術や抗がん剤治療、放射線治療の後に社会復帰するというケースも多くあります。男性の60%、女性の48%ががんになる時代ですから、医学生のみなさんも卒業して医師になったら、がんの患者さんを主治医として診ることになる場合も多いでしょう。
がんと診断されることは、患者さんにとって相当なショックを伴います。たとえ治療可能だとしても、告知された瞬間に死を想起する人も多いでしょう。苦しい治療に耐えられるのか、その間仕事はどうするか、本当に治るのか…など不安は尽きないでしょうし、治療終了後、再発する可能性に怯えながら暮らす人も少なくありません。
そう考えてみると、患者さんや家族の不安やつらさを和らげる緩和ケアの考え方は、決して終末期にのみ適用されるべきものではないということがわかると思います。だから私たち日本緩和医療学会は、がんと診断された時からの緩和ケアが重要だと考えているのです。
死について考える機会を持つことの重要性
日本人は生と死について考える機会が少ないのではないかと思います。日本には70年も戦争がなく、世界一の長寿国でもあり、人は必ず死ぬとわかっていても、実際に自分が死ぬことまで想像していない人が圧倒的に多いように思います。医学生の中でも、「1年後、生きていないかもしれない」などと考えたことがある人はほとんどいないのではないでしょうか。実は70代・80代の人も同じなのです。
そういうところに、がんは突然訪れます。だから、がんと診断されてはじめて死を想起する患者さんも多い。そうなったとき、主治医であるみなさんが、患者さんの生と死にしっかり向き合い、思いやることができるかどうか。私は、みなさんが一度でも腰を据えて生と死について考えたことがあるかどうかで、患者さんへの接し方が大きく変わってくるのではないかと考えています。
だから私は、大学で教えている学生には、「もし今『あと3か月しか生きられない』と言われたら自分なら残された時間に何をするかを真剣に、それも24時間考え続けてみてほしい」と伝えています。後から卒業生に、「どんなことを24時間真剣に考えたか」と聞いてみると、それぞれ、内容や感じ方は違いますが、「自分が死ぬことなんて考えたこともなかったけれど、やってみてとても勉強になった」と話してくれる学生が多いです。
みなさんも、国家試験が終わってから就職までの休みの間に、是非この“試み”を経験してほしいと思います。もちろん、何をしたから正解というものはありませんが、この試みをやること自体に大きな意味があると私は考えています。
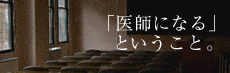


- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:西脇 聡史先生
- Information:October, 2014
- 特集:緩和の視点 患者の生に向き合う医療
- 特集:緩和ケアの基本的な考え方
- 特集:専門的緩和ケアの3つの現場 緩和ケアチーム
- 特集:専門的緩和ケアの3つの現場 ホスピス・緩和ケア病棟
- 特集:専門的緩和ケアの3つの現場 在宅緩和ケア
- 特集:医師に求められる「緩和の視点」木澤 義之先生
- 特集:医師に求められる「緩和の視点」細川 豊史先生
- 同世代のリアリティー:子どもを保育する 編
- チーム医療のパートナー:臨床心理士
- チーム医療のパートナー:精神保健福祉士
- 10号-11号 連載企画 医療情報サービス事業“Minds”の取り組み(後編)
- 地域医療ルポ:島根県隠岐郡西ノ島町|隠岐島前病院 白石 吉彦先生
- 10年目のカルテ:整形外科 八幡 直志医師
- 10年目のカルテ:整形外科 頭川 峰志医師
- 医師の働き方を考える:多様性を認め、働き続けやすい環境をつくる
- 医学教育の展望:高校からの9年間で人間力豊かな医師を養成
- 大学紹介:順天堂大学
- 大学紹介:埼玉医科大学
- 大学紹介:岐阜大学
- 大学紹介:鹿児島大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 第2回医学生・日本医師会役員交流会開催!
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- 医学生の交流ひろば:3
- FACE to FACE:櫛渕 澪 × 梅本 美月

