医学教育の展望:
医療におけるコミュニケーション教育(前編)
現在の医学部の卒前教育では、医学的知識を学ぶことに重きが置かれていた時代から、模擬患者を招いた面接のトレーニングなど、患者とのコミュニケーションを意識した教育も重視する時代に変わりつつある。しかし、医師として患者とどう対峙するべきか、患者と共に診療方針を決めるとはどういうことかを、学生の頃から学び考える機会は多くない。今回は、患者・医療者間の関係について考察し、著書やWEB媒体などで広くその考えを発信している尾藤誠司先生にお話を伺った。
医師は医学と患者をつなぐインターフェース
まず、医師とは患者にとってどのような存在であるかということについて、尾藤先生のお考えを伺った。
「医師とは、患者さんにとっては医学のインターフェースのような存在だと私は考えています。この医学という概念のなかには、エビデンスや効果・効能、治療の効率など全てが含まれます。診療の過程で、患者さんは当事者として、医学という知の体系を理解している人(=医師)から情報を得て、対話をし、意思決定をしていくことになります。その意思決定には、患者さんの感情や、ここに至るまでの経緯(文脈)といったものが、重要な要素として必ず関わってきます。医師は、様々なコミュニケーションの中で患者さんの感情や文脈をとらえ、医学的な知見を踏まえて、医学と患者さんとの間を媒介する。そういう存在だと思います。ですから、医師は、患者さんの抱える不安や恐怖、それまでの生き方や生活背景なども知ろうとしなければなりません。」
コミュニケーション教育の場はどこか
では、そのインターフェースとしての役割を果たす医師を育てるためには、どのような教育が必要だろうか。尾藤先生は、コミュニケーション教育は必要ではあるが、卒前教育や臨床研修に取り入れるのは限界があるのではないかと語る。
「医療におけるコミュニケーション教育とは、医学の知見と人の感情を結びつける教育だと私は考えています。ただ、特に学生のうちは、医学の知識を育む場と感情の豊かさを育む場は分けた方が良いと思っています。まずは専門職として必要な医学知識をしっかり学ぶべきでしょう。もちろん、臨床に出てから大切なのは知識だけではないということは、覚えておいてほしいですが。
人間の感情の機微を知るためには、自分が当事者になるのが一番です。感情の豊かさを育むためにも、部活やサークル活動、友人関係、恋愛などをどんどん経験してほしい。まだ見ぬ臨床のことを想像するより、学ぶことは多いと思います。」
医学教育の展望:
医療におけるコミュニケーション教育(後編)
「背中を見て覚えろ」でない、標準的なトレーニングを
尾藤先生は、自らが所属する総合内科のレジデントに向けて、コミュニケーションスキルを高めるトレーニングを行っている。臨床における一つひとつの体験を振り返る場を設けることで、様々な感情の動きを学ぶという。
「患者さんが退院する際に、その事例について皆でレビューをしています。通常は1件につき10分程度ですが、特に大変だった事例に関しては、時間をかけて深くレビューを行うようにしています。
また、院内で『倫理コンサルテーション』という場が設けられており、倫理的に難しい事例を多職種で話し合っています。この会は、実際にその事例にどう対応していくかという問題解決の場であるのと同時に、そこで悩んでいる医療者の感情を知り、皆で承認するという場にもなっています。
患者さんの感情や文脈という複雑なものに向き合う以上、医療者も当然、壁にぶつかったり、悩んだりすることはあります。そのときに自分が何に悩んでいたのか、そこにはどんな葛藤があったのかに気付くことが、成長につながると私は考えています。」
こうした学びは、体系的なカリキュラムにはしにくいかもしれない。しかしながら、ある程度の標準化は可能なのではないかと尾藤先生は言う。
「医学と感情を結びつけることは、例えば古典落語を面白く演じることや、美味しい寿司を握ることのような、技芸に近いことだと私は思っています。ただ落語を暗記するだけならそう難しくないかもしれませんが、深みや高みを目指そうと思ったら、とにかく経験が必要になる。けれども、多くの技芸のように『背中を見て覚えろ』というだけでは、質を保つことができない。一定のカリキュラムで、ある程度までは身につけられるようにしていきたいですね。」
「生身の人間だからこそ」できることで価値を発揮
とはいえ、全ての医師がインターフェースになる必要はないと尾藤先生は言う。
「患者の感情や文脈と向き合うよりも、ひたすら高度な手技を極めていくことに向いている医師もいます。医療全体の進歩を考えても、そちらに専門性を発揮する医師がある程度は必要です。
しかし、今後ますますインターフェースの役割は重要になってくるだろう、とも思っています。医療界においても、AIやロボットが活躍する未来がそう遠からずやって来るでしょう。その中で医師が専門職として価値を発揮するためには、患者さんの感情や文脈という、生身の人間でなければ扱いにくいものとしっかり向き合っていくことが大事になるのではないでしょうか。」
最後に、医学生へのメッセージを頂いた。
「患者さんの感情や文脈と向き合うことは、技術の向上や症例数を積み重ねていくことと比べてアウトカムの可視化が難しく、評価されにくいのではないかと感じる人もいるかもしれません。けれども、日々の業務の中で、患者さんや他職種からのニーズやリスペクトを実感できる、素晴らしい営みですよ。その楽しさを、医師の先輩として示していければ、と思っています。」

(東京医療センター 臨床研修科 医長)
1990年、岐阜大学医学部卒。国立東京第二病院(現・東京医療センター)、国立佐渡療養所での勤務、UCLAへの留学等を経て、現在は東京医療センターで総合内科医として勤務しながら、研修医の教育にも携わる。
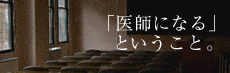


- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:淺村 尚生先生
- Information:Spring, 2018
- 特集:医師と研究
- 特集:基礎研究に携わる医師 鈴木 一博先生(大阪大学免疫学フロンティア研究センター 免疫応答ダイナミクス研究室)
- 特集:臨床研究に携わる医師 田中 里佳先生(順天堂大学医学部 形成外科学講座)
- 特集:臨床研究に携わる医師 田代 泰隆先生(九州労災病院 整形外科・スポーツ整形外科)
- 特集:社会医学研究に携わる医師 辻 真弓先生(産業医科大学医学部 産業衛生学講座)
- 特集:日本医学会会長に聴く 門田 守人先生(日本医学会 会長)
- 「食べる」×「健康」を考える③
- 同世代のリアリティー:薬剤師 編
- チーム医療のパートナー:看護師(緩和ケア・急性期)
- 地域医療ルポ:香川県木田郡三木町|松原病院 松原 奎一先生
- レジデントロード:麻酔科 長谷川 源先生
- レジデントロード:救急科 太田 美穂先生
- 医学教育の展望:医療におけるコミュニケーション教育
- 医師の働き方を考える:産業医として、子育て中の医師として、 日本社会の働き方改革に貢献したい
- 日本医科学生総合体育大会:東医体/西医体
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- 日本医師会の取り組み:受動喫煙の防止
- 地域医療の現場で働く医師たち 第6回「日本医師会 赤ひげ大賞」表彰式開催
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- 医学生の交流ひろば:3
- 日本医師会とドクタラーゼについて
- FACE to FACE:鈴木 あみ×西原 麻里子

