令和4・5年度会内委員会答申・報告書
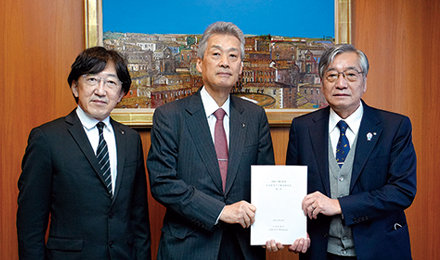
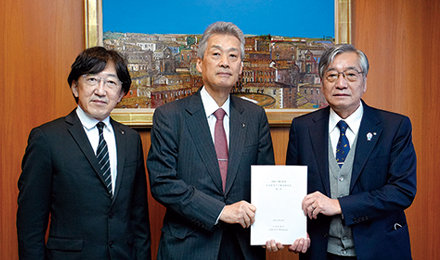
小児在宅ケア検討委員会はこのほど、会長諮問「医療的ケア児の自立を支援する地域共生社会の実現に向けて」に対する答申を取りまとめ、中尾正俊委員長(大阪府医師会副会長)より松本吉郎会長に提出した。
答申は、(1)医療的ケア児支援センター、(2)こども家庭庁、(3)小児在宅医療体制の整備・充実、(4)移行期医療、(5)保育・教育、(6)小児の緩和ケア、(7)保護者への支援、(8)市町村の協議の場、(9)障害福祉サービスの底上げ、(10)自立支援、(11)災害対策―で構成されている。
(3)では、都市型の医療圏と過疎地域型の医療圏では医療ニーズや医療提供体制が異なることから、それぞれに分けて、地域の小児科医や成人を診る在宅医の医療的ケア児の診療への関わり方等が詳細に述べられている。
また、福岡県で新たにスタートした、在宅医療とNICUを有する病院との中間施設としての「小児等地域療育支援病院」制度や、山形県における病院主治医と在宅主治医の二人主治医体制、小児科主治医同行訪問事業についても紹介されている。
(8)では、保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関が連携を図るための「協議の場」について、各地域の事例を示しつつ、現状では郡市区医師会の参画が少ないことから、積極的な関与を求めている。
(11)では、今回の能登半島地震において、石川県医療的ケア児支援センターが災害時小児周産期リエゾンらに医療的ケア児と家族の情報を迅速に提供したことによって、速やかな避難につながったこと等を紹介。全国の医療的ケア児支援センターにおいても平時から積極的に災害対策に取り組むよう求めている。
また、医療的ケア児を対象とした「避難行動要支援者名簿」や「個別避難計画」の作成等については地域によってばらつきがあることから、医師会からの市町村への働き掛けを要請。その他、愛知県の瀬戸旭医師会が実際に医療的ケア児や家族に参加してもらって、ICTを用いた防災訓練を行っている事例などを紹介している。



