医師への軌跡
医師の大先輩である先生に、医学生がインタビューします。
患者の求める「臨床」-bedside-を大切に
高山 義浩
沖縄県立中部病院 感染症内科・地域ケア科 副部長

地域のニーズに耳を傾ける
真喜志(以下、真):高山先生は非常に特異なご経歴をお持ちです。まず、医師を目指されたきっかけは何でしたか?
高山(以下、高):医学科入学前にカンボジアの農村で社会調査をしていました。そこで多くの乳幼児が感染症で死亡していることはわかるのですが、その原因も、どうすれば助けられるのかも全くアセスメントできなかったのです。現場にいながら、自分には何も分からない。何もできない。その無力感が、医師を目指したきっかけでした。
真:そして医学部卒業後、HIV診療に携わられたのですね。
高:はい。学生時代に途上国を旅していて、社会的弱者にエイズが蔓延していることに衝撃を受けたからです。世界的にエイズは深刻な問題でした。まずはHIV診療ができる医師を目指して、九州のHIV診療の中核拠点である国立病院九州医療センターで臨床研修を受けました。その後もHIV診療へのこだわりが強かったのですが、ある日、とある村の診療所長と酒を飲んでいたときに、こう諭されたんですね。「自分のやりたいことばかり言う医師は、地域医療には向かないよ。地域でどんな医師が求められているかに耳を傾けるべきじゃないか」。
医師としての生き方を考えさせられました。「自分のやりたいことを突き詰める道もあるけれど、地域のニーズに応じて自分をカスタマイズできる医師になりたい」と思って、地域医療で知られた佐久総合病院総合診療科の専門研修医になりました。その後も仕事を転々としていますが、自分自身としてはニーズに従って働いてきたつもりです。
臨床とは、枕元で話を聴くこと
真:先生はその後、厚生労働省での新型インフルエンザ対策や地域医療構想策定支援、沖縄中部病院での地域ケア・在宅ケア推進など様々な活動に取り組まれます。多くの葛藤や模索を乗り越えてきた先生のこれまでのご経験のなかで、特に人生を変えた出来事は何でしたか?
高:医学生時代にイラクの医師や医学生と交流した経験は大きかったと思います。当時フセイン政権下にあったイラクは経済制裁下にあり、ほぼ社会機能が停止していました。先進的な医療を提供していたはずのバグダッド大学病院もライフラインが止まっていて、ほとんどの医療機器は壊れていました。医薬品も十分になく、酷暑のなかで腐ってゆく患者の臭いが病室に漂っていました。それは、大学病院の姿ではありません。いわば「患者の収容所」と呼ぶべき状況でした。しかし、それでも大学病院は開いていたのです。理由を医学部長に尋ねると、「患者が臨床を求めているからだ」と答えました。「患者にとって本当に必要なのは、最新の設備ではない。医療者が、どんな場所や時間であっても患者のそばにいるということなんだ」。
ヒポクラテスは、医療で一番大切なことはクリニコスκλινικόςであると弟子に示したそうです。「病人の枕元で話を聞くこと」という意味でした。その後クリニック clinicとなり、明治の先人は「臨床」と訳しました。素晴らしい訳ですね。
私自身は、日本の地域医療の見通しは厳しいと感じています。技術はあっても、今よりもっと、できることは限られていくでしょう。そのとき、日本の医療者が絶望しないことが重要で、諦めて患者のもとを離れることがないようにしなければなりません。問われているのは臨床への想いです。
真:学生時代に大切にした方がいいと思うことはありますか?
高:部活でも何でも、打ち込むこと自体に意味があると思います。ただ、打ち込むことに迷っているのなら、旅に出てみてはどうでしょう? もちろん一人で。日常の自分を客観的に見直す良い手段だと思います。
高山 義浩
沖縄県立中部病院 感染症内科・地域ケア科 副部長
東京大学医学部保健学科卒業。フリーライターとして活動後、山口大学医学部医学科に入学。在学中は途上国や中央アジアを旅するなど、様々な立場の人と出会い、話を聴く経験を重ねる。2002年に卒業後、感染症診療や地域医療に従事。厚生労働省での新型インフルエンザ対策を経て、沖縄県立中部病院にて感染症診療の傍ら地域ケア科の立ち上げに携わる。2014年、厚生労働省にて地域医療構想の策定支援に取り組んだのち、現在に至る。
真喜志 依里佳
琉球大学医学部 5年
私はアジアの貧困地域に貢献したくて医師を志しましたが、同じような志を持つ人と出会う機会も少なく、進路に悩むことが多くあります。高山先生は遠い存在のように感じられますが、ご著書を読むとその時々の等身大の悩みなども綴られていて親近感が湧きました。今回はご著書に書いていないようなお話まで聞かせていただくことができました。ぜひ、今後の糧にしたいと思います。
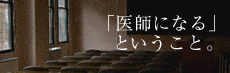


- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:高山 義浩先生
- Information:Winter, 2020
- 特集:他者に学ぶ、他者と学ぶ ~医師と医学生の学びを問い直す~
- 特集:「学び」は「どこ」で生じる?~人は「状況の中」で学び合っている~
- 特集:医学教育の中で「他者」と「学び合う」ための仕掛け
- 特集:Interview1 春田 淳志先生 筑波大学医学群 医学教育企画評価室(PCME) 医学医療系 地域医療教育学/ 総合診療グループ 准教授
- 特集:Interview2 大嶽 浩司先生 昭和大学医学部 麻酔科学講座 主任教授
- 特集:医師と医学生の学び~より良い医師を目指して~
- 同世代のリアリティー:カメラマン 編
- チーム医療のパートナー:療育に関わる専門職【後編】
- 地域医療ルポ:神奈川県横須賀市|三輪医院 千場 純先生
- レジデントロード:内分泌・代謝・糖尿病内科 今村 修三先生
- レジデントロード:小児外科 宮嵜 航先生
- レジデントロード:総合診療科 田中 孟先生
- 医師の働き方を考える:がんと闘病しながら、研究も私生活もアクティブに
- 日本医師会の取り組み:健康スポーツ分野における様々な取り組み
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:宮崎大学「地域包括ケア実習」
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- 医学生の交流ひろば:3
- 医学生の交流ひろば:4
- 日本医師会後援映画「山中静夫氏の尊厳死」
- FACE to FACE:山下 さくら × 河野 大地

