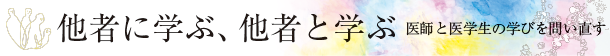
Interview 私のライフヒストリー
異なる価値観を持つ「重要な他者」と出会い、
相手の枠組みで考える(前編)
教育に携わるようになったきっかけ
――春田先生は総合診療をバックグラウンドとして、医学教育や多職種連携教育の研究をされています。まず、教育に関心を持った経緯を教えてください。
春田(以下、春):私は東京の王子生協病院という150床ぐらいの病院で臨床研修を受けました。その病院はいわゆる屋根瓦式で、先輩が後輩を教えるのが当たり前という環境だったので、ごく自然に教育に携わるようになりました。医師6年目に、指導医から「個人を教えるだけではなく、病棟全体をマネジメントする役割が必要なのではないか」と言われたことがきっかけで、それまでこの病院にはなかった「チーフレジデント制」の立ち上げにも携わりました。
――そのような環境では、卒業直後の研修医にも、病院組織や多職種連携の全体像がおおよそ理解できるものですか?
春:いえ、そんなことは全くないんです。臨床研修の一環として1か月間、病院の中の他部門や周囲の診療所、地域の様々なリソースを見て回る機会もありましたが、それがチームだ、組織だという実感はありませんでした。特に臨床研修の2年間は、「自分がいかに能力を獲得するか」ということばかりに気を取られ、チームや組織、多職種連携といったことがなかなか自分事に思えませんでした。
――では、チームや組織で学ぶことに関心を持ちはじめたのはいつ頃でしたか?
春:一つの転機は、臨床研修医の頃です。当時は同期で日々集まって、1日の振り返りをしていました。そのなかで「患者さんのことばかり言っていて、自分のことを振り返ることができていないのでは?」と同僚に指摘されたことがありました。その時初めて、患者さんという「他者」と関わるなかで、自分に何ができて、何ができていなかったのかを見つめ直していなかったと気付きました。そこから学びに対する姿勢が変わり、自分の学びを相対化するようになりました。
もう一つは、初めて主治医になって、「自分一人では何もできない」と感じた時ですね。オーダー一つとっても、その先には看護師さんや薬剤師さんがいて、その人たちが働きやすいように動かないと、自分たちもうまく治療ができないと実感するようになったんです。自分がチームの一員だと強く感じるようになってからは、チーム・組織のメンバー間には「自分は知っているけれど他の人は知らない」というような様々な知識や技術の凸凹があって、その強み・弱みが患者さんのケアの質に強く影響するということがわかってきました。それを互いに知り、学び合う環境がなければ、ケアの質向上につながらないと考え、チームで学習会を開いたり、業務外で飲み会を開いたりするようになりました。
「連携」は難しいことだと気付く
 ――その後、先生は大学院に進学され、本格的に教育について研究されるようになりますが、そのきっかけは何でしたか?
――その後、先生は大学院に進学され、本格的に教育について研究されるようになりますが、そのきっかけは何でしたか?
春:後期研修が終わった後、医師7年目で病棟医長を1年間務め、医療者教育や組織学習についても学び、実践するようになりました。緩和ケアチームのプロジェクトの立ち上げなどにも携わり、「こうやってチームを作っていけばいいんだ」という実感もありました。ところが、いざ自分の取り組みをポートフォリオ*としてまとめようとした時、「なぜそれができるのか」を人に伝えることができないと気付いたのです。特に、医療者教育において「この分野でどのような知見が蓄積されていて、自分は何をどのように実践したのか」を説明できないと、後進を育てられないと感じ、大学院で理論や背景的知識を学びたいと思いました。
いざ大学院に入り、大学病院の臨床を見たりするなかで、王子生協病院で行われているような連携が「当たり前」ではないということに気付かされました。「王子生協病院ではできていたことが、他の病院ではなぜできないのか?」と関心を持つようになり、さらに2011年にWHOから出た多職種連携教育(Interprofessional Education,IPE)のレポートを見て、「WHOが出さなければいけないぐらい、連携って難しいものなのか」「これが学問になるのか」と衝撃を受けたのです。そのことを調べるうちに、国際的にIPEの情報を発信しているイギリスのCAIPE(Centre for the Advancement of Interprofessional Education)という団体に出会いました。大学院の留学プログラムともタイミングが合ったことも後押しになり、イギリスに1か月滞在し、多職種連携を学ぶことになりました。
――イギリスでは具体的にどのようなことを学んだのですか?
春:IPEに関する理論の本を読みながら、実際の連携を視察するという、理論の学習と実践の観察を繰り返しました。この時の経験は、思い出しても自分にとって非常に贅沢な時間でした。イギリスでは、小さい頃から「自分の意見を持つ」ということを教え込まれているためか、共通の目標に向かってそれぞれが率直に意見を交わし合う文化ができていました。自分が専門職として見た情報から「だから私はこう思う」と説明し、互いに対話しながら「この患者さんにとって一番大切なのはこれなんじゃない?」「じゃあそのためにはこれが必要だね」と方向性を定めていくのです。各人が何をするかを細かく定めずとも、目標とする方向性について合意ができ、それに向かって各専門職が専門性を持ってアプローチできる、そんな状態がチーム医療の理想なのだと感じました。もちろんイギリスでも現実はそんなに簡単ではありません。状況が変化することで方向性も変わっていくことはありますし、誰かが何かを見落としてしまうこともある。けれど、足りない部分を互いに補い合い、状況に応じて共に試行錯誤する、その過程がまさにチーム学習や組織学習だと実感しました。
*ポートフォリオ…実践と振り返りのレポート。
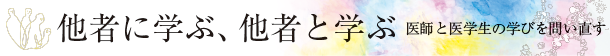
Interview 私のライフヒストリー
異なる価値観を持つ「重要な他者」と出会い、
相手の枠組みで考える(後編)
「他者」と出会うことの大切さ
――チーム医療・多職種連携が重視される今、「多職種を含めたチームで何ができるか」を考えられる医師がますます求められています。しかし医学生の段階では、その認識には至りにくいとも思います。
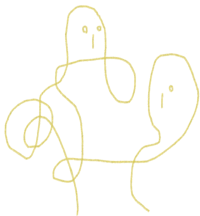 春:そうですね。医学生のうちは、まずは卒業と国家試験合格がリアルに感じられる目標です。それらが唯一の「正解」を求める評価だとすると、効率的に唯一解を求めることが良いことだと刷り込まれます。テストで高得点をとる、高評価を得るということにとらわれてしまうのです。
春:そうですね。医学生のうちは、まずは卒業と国家試験合格がリアルに感じられる目標です。それらが唯一の「正解」を求める評価だとすると、効率的に唯一解を求めることが良いことだと刷り込まれます。テストで高得点をとる、高評価を得るということにとらわれてしまうのです。
例えば現在、筑波大学の総合診療科の4週間の臨床実習では、「健康の社会的決定要因(SDH)」という視点から、患者さんの上流にある背景を探り、今との関連を整理する課題を出しています。すると学生は、SDHに記載されている10個の要因すべてに当てはまるような、医療者から見て「不幸そうな」患者さんを探そうとします。患者の立場に立とうとせず、無意識に自分の思考の枠組みに患者さんを当てはめようとしてしまうんです。
SDHには何か明確な基準があるわけではありません。逆に言えば、どんな人の健康も、良い意味でも悪い意味でも社会的・経済的に影響を受けています。現場に出たら、患者さんを取り巻く社会的・経済的状況を想像しながら、より良い医師患者関係を構築し、それぞれの生活があっての検査・治療などを考えなければなりません。だからこそ、自分とは異なる価値観で生活をしてきた様々な人と話し合いながら、一緒に考えていくことが求められるのです。この実習でも、「当てはまる患者さんがいなくて困る」という医学生がいます。そんな学生には、訪問診療や訪問看護がSDHを理解しやすい場面であることを伝えます。訪問診療では、その人の生活や生活史、家族との関係、生き様などが垣間見えます。自分と文化も価値観も異なる方の上流にある様々な要素が、目の前の患者さんの「今」や「これから」につながることが想像できます。そうした経験を積み重ねて、生活への想像力を養ってほしいと思います。
――では、今の段階から医学生にできることはありますか?
春:IPEを通じて看護学生や薬学生といった「重要な他者(significant others)」と出会い、自分の枠組みではなく相手の枠組みに入って考えてみる経験は、とても意義があると思います。医療だけでなく、「重要な他者」のジャンルを広げ、多様な価値観から見えてくる世界について知る経験を、医学生のうちからしておくことは有効なのではないでしょうか。近年は医学教育においても、医療社会学や医療人類学といった、相手の文化をしっかり観察するような方法論がモデルカリキュラムに取り入れられはじめていますし、筑波大学では神栖市と協力して、青果店、太陽光発電、弁護士事務所など様々な職場に出向き、一緒に仕事をしたり、話を聴く機会を臨床実習の中に取り入れています。SDHの視点で、患者さんの上流にある背景を探る課題もその一つですね。こうした体験を通じて、自分の他に色々な人たちがいることを肌で感じることが、いずれ「みんなで学ぶ」という価値観につながっていくのではないかと思います。
 春田 淳志先生
春田 淳志先生
筑波大学医学群 医学教育企画評価室(PCME)
医学医療系 地域医療教育学/ 総合診療グループ 准教授
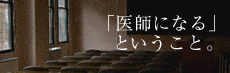


- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:高山 義浩先生
- Information:Winter, 2020
- 特集:他者に学ぶ、他者と学ぶ ~医師と医学生の学びを問い直す~
- 特集:「学び」は「どこ」で生じる?~人は「状況の中」で学び合っている~
- 特集:医学教育の中で「他者」と「学び合う」ための仕掛け
- 特集:Interview1 春田 淳志先生 筑波大学医学群 医学教育企画評価室(PCME) 医学医療系 地域医療教育学/ 総合診療グループ 准教授
- 特集:Interview2 大嶽 浩司先生 昭和大学医学部 麻酔科学講座 主任教授
- 特集:医師と医学生の学び~より良い医師を目指して~
- 同世代のリアリティー:カメラマン 編
- チーム医療のパートナー:療育に関わる専門職【後編】
- 地域医療ルポ:神奈川県横須賀市|三輪医院 千場 純先生
- レジデントロード:内分泌・代謝・糖尿病内科 今村 修三先生
- レジデントロード:小児外科 宮嵜 航先生
- レジデントロード:総合診療科 田中 孟先生
- 医師の働き方を考える:がんと闘病しながら、研究も私生活もアクティブに
- 日本医師会の取り組み:健康スポーツ分野における様々な取り組み
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:宮崎大学「地域包括ケア実習」
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- 医学生の交流ひろば:3
- 医学生の交流ひろば:4
- 日本医師会後援映画「山中静夫氏の尊厳死」
- FACE to FACE:山下 さくら × 河野 大地

