日本医師会の取り組み
日本医師会雑誌
最新の学術的知見に触れる機会を提供
日本医師会が発行している医学総合雑誌「日本医師会雑誌」についてご紹介します。
日本医師会雑誌とは
日本医師会雑誌(以下、日医雑誌)は1921年に『醫政』として創刊された、日本医師会の歴史ある会報誌です。1937年にその名称を現在の『日本医師会雑誌』に改めるなど、幾たびかの変更・改正を経ながら、毎月1日発行の月刊誌と年2回の特別号(生涯教育シリーズ)という現行の形式に整備され、今日に至っています。毎号の発行部数は13万部を超える、日本最大級の医学総合雑誌です。
日本医師会は、47都道府県医師会の会員から組織される学術団体です。日医雑誌は、医療制度や医療政策に関する内容だけでなく、学術的な内容を主眼にして構成されています。
多岐にわたる特集テーマ
日医雑誌は、毎号異なるテーマの特集と、各科の診療のトピックス・新薬紹介・最新の治療法の紹介といった内容で構成されています。各号の特集テーマは多岐にわたり、自分の専門領域以外の知識を得るためにも適した内容となっています。
最近の特集テーマを一覧にまとめました(表1・表2)。臨床現場における今日的なテーマも多く取り上げられています。医学生の皆さんにとっても、実習などで役に立ちそうだと感じるものがあるのではないでしょうか。
生涯教育制度と日医雑誌
日医雑誌は、日本医師会の生涯教育制度の一環としても位置づけられています。
日本医師会生涯教育制度とは、日本医師会が提供する医師の自己学習・研鑽をサポートするための種々の枠組みの総称です。医師自身の内発的動機に基づく継続的な自己啓発、すなわち、プロフェッショナル・オートノミーを理念とし、生涯学習を有効に行うための支援体制の整備を目的として運用されています。生涯教育制度には医師免許取得直後から参加でき、連続した3年間に、生涯教育制度が定める単位(学習時間)とカリキュラムコード(学習した領域)を合計60以上取得することで、「日医生涯教育認定証」が発行されます。
医師は、日々進歩する医学・医療について、常に知識を深め、技術を研鑽していかなければなりません。しかし、臨床研修や専門研修を終えると、大学病院等の教育機能が整った医療機関を離れることも少なくないため、新しい知識を学び、技術をアップデートする機会が減ってしまう人もいるでしょう。
そのため日本医師会では生涯教育制度を整備し、様々な学習教材・機会を提供しています。具体的には、生涯教育カリキュラムを主軸としたWEB教材の日医eーラーニングや、多様なワークショップセミナー、そして日医雑誌もその中に含まれているのです。
日医雑誌は、生涯教育制度の単位の取得にも直接関係しています。毎号の特集に関連した問題に解答し、60%の正答率を得ると単位を取得することができます。
このようにして日本医師会は、地域で臨床に従事する勤務医や開業医が学び続け、新しい知見に触れる機会を提供しています。
日医雑誌を読むには
日医雑誌は、日本医師会員や都道府県・郡市区等医師会館、関係官庁、各大学医学部の図書館などに送付されています。医学生の皆さんも、大学の図書館で手に取って読むことが可能です。また、日本医師会が所有する各種書籍等を収蔵したオンラインサービス日本医師会e-Library(日医Lib)上でも閲覧できます。
日医雑誌は毎号、幅広いながらも濃密な情報を取り扱っています。中には医学生の皆さんの興味に合った内容もきっと取り上げられているはずです。ぜひ一度、大学の図書館などで触れてみてください。
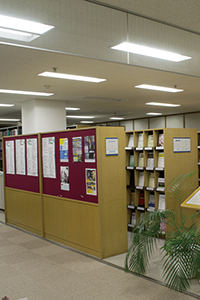
『日本医師会雑誌』は毎号各大学図書館に送付されています。
興味のある方はぜひ手に取ってみてください。
(表1)『日本医師会雑誌』特集テーマ(一部)
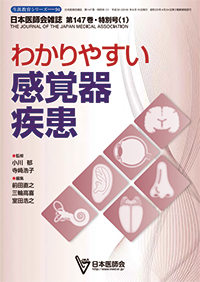
| 明日を拓く乳がん診療-新たなチームアプローチ | H30.6月 |
| IgG4関連疾患 -21世紀に生まれた新たな全身性疾患 | H30.5月 | 抗酸菌感染症の最新情報と展望 | H30.4月 |
| 性感染症-今,何が問題か | H30.3月 |
| 救急医療における外傷診療の最前線 | H30.2月 |
| 骨粗鬆症の診断と治療update | H30.1月 |
| 臓器移植法施行から20年: わが国における臓器移植の現状と展望 | H29.12月 |
| 摂食障害 | H29.11月 |
| 心臓外科・血管外科の現状と展望 | H29.10月 |
| 学校健康診断-健診・検診と事後措置 | H29.9月 |
| 日本における緩和ケアの現状と今後の方向性 -緩和ケアを俯瞰して | H29.8月 |
| 失神の臨床 | H29.7月 |
| 真菌症診療-深在性から表在性まで | H29.6月 |
| 国際的に脅威となる感染症とその対策 | H29.5月 |
(表2)特別号(生涯教育シリーズ)テーマ(一部)

| わかりやすい感覚器疾患 | H30.6月 |
| 環境による健康リスク | H29.10月 |
| 脳血管障害診療のエッセンス | H29.6月 |
| 皮膚疾患ぺディア | H28.10月 |
| アレルギー疾患のすべて | H28.6月 |
| Electrocardiography A to Z | |
| -心電図のリズムと波を見極める | H27.10月 |
| ロコモティブシンドロームのすべて | H27.6月 |
| 感染症診療update | H26.10月 |
| 痛みのマネジメントupdate | |
| -基礎知識から緩和ケアまで | H26.6月 |
| 神経・精神疾患診療マニュアル | H25.10月 |
| 高血圧診療のすべて | H25.6月 |
| 消化器疾患診療のすべて | H24.10月 |
| 小児・思春期診療 最新マニュアル | H24.6月 |
| 症状からアプローチするプライマリケア | H23.10月 |
| 画像診断update―検査の組み立てから診断まで | H23.6月 |



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:木村 祐輔先生
- Information:Spring, 2018
- 特集:医師の仕事と診療報酬
- 特集:case study 脳梗塞の場合
- 特集:case study 大腿骨頸部骨折の場合
- 特集:教えて!中谷先生! ここが知りたい診療報酬
- 特集:column 診療報酬ってどうやって決まっているの?
- 特集:研修医・勤務医にできること
- 同世代のリアリティー:人事の仕事 編
- チーム医療のパートナー:看護師(皮膚・排泄ケア)【前編】
- レジデントロード:脳神経外科 片貝 武先生
- レジデントロード:内科 鈴木 あい先生
- レジデントロード:外科 宮﨑 佳子先生
- 日本医師会の取り組み:日本医師会雑誌
- 医師の働き方を考える:子どもたちの成長・発達と、お母さんたちの社会復帰を支援する
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- 医学教育の展望:次の100年を見据えた東京医科大学の教育改革
- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:滋賀医科大学「医療イノベーションの基礎」
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- 医学生の交流ひろば:3
- FACE to FACE:鈴木 優子×石橋 拓真

