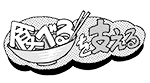 嚥下機能をきちんと見極める
嚥下機能をきちんと見極める


 野村 泰造 90歳
野村 泰造 90歳
20年ほど前に妻に先立たれた。息子夫婦が時折見舞いに訪れている。認知症が進んでおり、心機能も落ちている。
 甲斐 護(介護リーダー)
甲斐 護(介護リーダー)
老人ホームの介護リーダーで、野村さんの担当でもある。物腰やわらかな雰囲気。四堂先生を信頼している。
むせてしまう、本当の理由
野村さんは、食事中にむせることが増えてきたため、嚥下機能の低下が疑われています。誤嚥性肺炎の予防のため、先月からペースト状にしたミキサー食を提供されるようになりましたが、野村さんは気に入らない様子。食が進まず、低栄養も懸念されています。
この状況でまず検討しなければならないのは、「嚥下機能は本当に落ちているのか」という点です。本人の嚥下機能に問題がなくても、食事介助の仕方によってむせてしまうことがあるからです。例えば、食事中の姿勢に問題はないか、一度に口に入れる量が多すぎないか、口に食べ物を運ぶペースが速すぎないか、といったことに気を付けて、介助方法を見直してみる必要があります。また、体温に近い温度の食品は飲み込みにくいため、温かい料理は温かく、冷たい料理は冷たく提供するようにしたり、食前に口内を潤しておくといった工夫も有効です。
ミキサー食は、提供する側にとっては安全な優れた食事ですが、料理の味や匂い、食感が失われており、見た目にも美味しそうとは思いにくいため、食べる楽しみや意欲を低下させてしまうことがあります。まずは嚥下機能評価によって、どの程度の食事までは飲み込めるのかを正しく評価してもらい、その人の機能の許す範囲で充実した食事を摂ってもらうことが、QOLの維持・向上につながるでしょう。



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:キッティポン・スィーワッタナクン先生
- Information:Winter, 2019
- [新春対談]本庶 佑(京都大学 特別教授)×横倉 義武(日本医師会 会長)
- 特集:「食べる」を支える
- 特集:バランスの良い食事を用意するために
- 特集:噛む力を維持・向上させよう
- 特集:嚥下機能をきちんと見極める
- 特集:多職種カンファレンス ~「食べる」を多角的に支援する~
- 特集:医療機関における口腔ケア ~合併症予防の視点~
- 特集:地域の人たちの健康を保つ ~保健の視点~
- NEED TO KNOW:新専門医制度のこれから
- 同世代のリアリティー:国際協力 編
- 地域医療ルポ:静岡県下田市|河井医院 河井 文健先生、河井 栄先生
- レジデントロード:泌尿器科 塩見 叡先生
- レジデントロード:血液内科 辻 紀章先生
- レジデントロード:乳腺外科 酒井 春奈先生
- 医師の働き方を考える:つらい時も、医師としての仕事が心の支えになった
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:筑波大学「医療概論Ⅲ 健康教育 アルコール指導」
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- FACE to FACE:浅沼 翼×及川 孔

