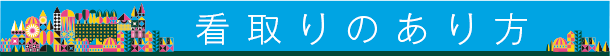
病院で看取る(前編)
麻酔科から緩和ケア病棟へ
――緩和ケア病棟で働くまで、どのようなキャリアを積んでいらしたのですか?
奥津(以下、奥):卒後は麻酔科に入局し、しばらく手術麻酔や集中管理などを担当していたのですが、専門医資格を取った後に進路を変更することにし、ペインクリニックで研修していました。するとその研修先の先生が、「緩和ケアをやってみたら?」と勧めてくださったんです。当時は、がん対策基本法が施行され、緩和ケアの様々な取り組みが行われつつあった頃でした。私自身はその時初めて「緩和」という言葉を聞いたのですが、静岡がんセンターの緩和ケア病棟で、3年ほど研修させてもらうことにしました。その後、この病院の緩和ケア病棟の立ち上げに携わり、それから7年ほど、ここで主にがん末期の患者さんの診療に携わっています。
看取りの全容を学ぶ
――緩和ケア病棟で、亡くなることが前提の方に長期間にわたって関わるということは、それまでのご経験とは随分異なるお仕事ではありませんでしたか?
奥:そうですね。看取るケースを何例も何例も経験して、ようやく人が亡くなる経過というものがわかってきました。
――麻酔科時代、ICUで患者さんが亡くなる事例は経験なさってきたと思うのですが、それとはまた違うものですか?
奥:はい。ICUでは、できることは全てやりますし、亡くなり方も劇的ですから、がん末期の看取りとは全く違いますね。
看護師さんも、急性期病棟から緩和ケア病棟に異動してくると、数か月は戸惑うようです。どういう経過を辿ることになるのか、それぞれの段階で家族にどういう声かけをしたらいいのか、本人に対して必要なケア・不要なケアはどう見極めたらいいのか…。がんの種類によって経過も違いますし、合併症が起こることもありますし、患者さんの背景によって介入の仕方も変わります。かなりの数のケースを経験しないと、看取りの全容が見えるようになるのは難しいですね。ただ、誰かが看取りの全体像、ロードマップを提示してくれる環境なら、半年も働けば、チームの一員としてしっかり看取りに対応することができるようになってきますよ。
リハビリテーション的な関わり
――こちらの緩和ケア病棟の患者さんは、基本的には積極的治療は中止された方ですよね。
奥:はい。急性期病院から直接転院してくる方もいますし、急性期から在宅にシフトしたけれど、家で看るのが難しくなり、入院してくる方もいます。「最後は自宅で」という方針で在宅療養していた方が、「やはり病院に戻りたい」という場合でも、前向きに受け入れたいと考えています。がん末期の場合、他の疾患のように入退院を繰り返す方は少なく、家から戻ってきた方は、そのまま病院で看取るケースが多いですね。
――なぜもう一度家に帰るのが難しいのでしょうか?
奥:がんの末期の場合、亡くなるまで2か月程度になると、ADLが急降下します。特に排泄ができなくなると、患者さん本人もご家族も大きなショックを受けるようです。ゆっくり進行する疾患であれば受容するための時間もとれますが、進行の速いがんの場合は、「それならば病院で看取ってほしい」と希望される方も多いんです。
ADLが急激に落ちていくなかでも、緩和ケアチームのリハビリ専門職は大事な役割を果たします。末期や緩和の局面でリハビリというと違和感があるかもしれませんが、機能を元通りに回復させることは難しくても、QOLやADLの維持のためのリハビリならできますし、いいリフレッシュの機会にもなるんですよ。
最後の数日は、ほぼ看護の領域ですね。医師からは、せん妄や出血など、「これから起こりうること」をご家族に説明して、不安を取り除くことが大事だと思っています。実際に目の当たりにすると、やはりショックを受けられますので。

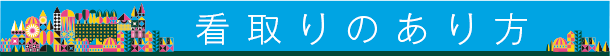
病院で看取る(後編)
開かれた緩和ケア病棟に

――患者さんやご家族からすると、家で看取るのが難しいとき、いつでも受け入れてくれるのはとてもありがたいことだと思います。一方、医療機関としては、常にベッドを空けておくわけにもいかないという難しさもあるのではないかと思うのですが。
奥:そうですね、そこはバランスを取らなければなりません。そう考えた時、必要なのは院外との連携だと思います。私はこの緩和ケア病棟を、常に地域や院内の他部署に開かれたものにしたいと思いながらやってきました。病棟内で話し合うべきことは話し合いつつ、外にもしっかりとアプローチしていくことが大事だと思っています。
――具体的にどのようなアプローチを行っているのですか?
奥:緩和ケア病棟のスタッフが、積極的に地域に出ていくようにしています。例えば、ベッドが満床の時に入院希望があった場合、患者さんの家まで直接足を運んでみる。そこに訪問看護師さんがいればディスカッションもできますし、ご家族に「大丈夫、待ってるからね」「来週までがんばってね」と伝えるだけでも、心配や不安を取り除くことができ、その後がスムーズに進むんです。アウトリーチによって地道につながりを作り、少しずつでも顔が見える関係を築いていくところが肝なのかな、と考えています。




- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:後藤 理英子先生
- Information:Spring, 2017
- 特集:看取りのあり方
- 特集:看取りの全体像 在宅の場合を例に
- 特集:人生の最終段階の経過
- 特集:病院で看取る
- 特集:家で看取る
- 特集:看取りを学ぶ
- 医科歯科連携がひらく、これからの「健康」④ これからの医科歯科連携を考える
- 同世代のリアリティー:大学職員 編
- 地域医療ルポ:秋田県横手市|山内診療所・三又へき地診療所 下田 輝一先生
- チーム医療のパートナー:看護師(手術室)
- 10年目のカルテ:皮膚科 飯沼 晋医師
- 10年目のカルテ:形成外科 佐野 仁美医師
- 10年目のカルテ:眼科 浪口 孝治医師
- 日本医師会の取り組み:日本医師会の医師賠償責任保険
- 医師の働き方を考える:患者のため、そして医療従事者のためにより良い制度を作っていきたい
- 医学教育の展望:学生の能動的な学びをサポートする
- 大学紹介:群馬大学
- 大学紹介:東京医科歯科大学
- 大学紹介:九州大学
- 大学紹介:和歌山県立医科大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- FACE to FACE:池尻 達紀×荘子 万能

