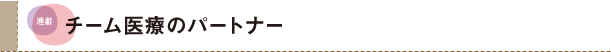
看護師(手術室)(前編)
手術全体をコーディネート
 ――まず、手術室の看護師のお仕事について教えてください。
――まず、手術室の看護師のお仕事について教えてください。
和田(以下、和):手術看護の根幹は、手術に関わる一人ひとりの役割をうまくつなぎ、チーム全体のムードやコミュニケーションを整えるところにあると思います。患者さんをはじめ、執刀医・麻酔科医・臨床工学技士・他の看護スタッフ、また手術に必要な道具や器械など、手術室の環境や雰囲気全体に気を配るのが、私たちの仕事です。
高橋(以下、高):手術室看護師の仕事は、大きく「器械出し」と「外回り」に分けられます。
器械出しの仕事は、事前に術式や患者さんに合わせて手術で使用する器械を準備し、術中には医師の指示に応じて器械を手渡すというものです。医療ドラマの手術シーンでもよく出てくる仕事ですね。医師に指示されてから用意するのでは間に合わないので、手術の流れを見ながら、いかに術者の先生の手を止めず、円滑に手術を進められるかに注意して仕事をしています。
和:外回りの仕事の時は、術中には術野から少し離れて手術室全体に目を配ります。足りない器械や薬剤が発生した時は、その準備をしたり、手術の記録や不潔野でのサポート、緊急事態のときに人を呼び集めるなど、様々な役割があります。
高:術前に患者さんにお会いして、不安や要望を聴き取るのも外回りの重要な仕事です。手術の既往がある方であれば、以前の手術の際負担に感じたことなどもお聞きします。手術は、医療者にとっては毎日のように繰り返されるものですが、一人ひとりの患者さんにとってはとても大変なできごとですよね。事前の訪問でしっかりコミュニケーションをとっておくことは、術中の安全管理はもちろん、術後のケアにもつながります。
手術中の体位を考える
――術前の綿密な準備が、円滑な手術につながるんですね。
高:はい。術中の体位についても、事前に入念に検討します。患者さんの体型・皮膚の状態・可動域などによって、適切な体位は変わってきますから。うっ血や褥瘡など、手術の傷以外で痛みが出ることを防ぐため、患者さんへの聴き取りを含め、様々な評価を行います。執刀医の先生が手術しやすい体位と、患者さんの負担にならない体位が一致しないこともしばしばありますから、両者にうまく折り合いをつけて調整するのが、看護師の工夫のポイントです。
和:ロボット支援手術の担当になった時、医師の先生と体位についてやり取りしたことは、特に印象に残っています。当院では、約1年前に手術支援ロボットを導入したのですが、前立腺悪性腫瘍のロボット支援手術では、頭の位置を30度ほど下げる、非常に特殊な体位を取るんです。そのため看護師の間で、患者さんの体にできるだけ負担をかけないためにはどうしたら良いか、じっくり検討していました。すると泌尿器科の先生方も、実際に体位をとるなどしながら、私たちと一緒に考えてくださったんです。また、麻酔科の先生も麻酔域について色々と提案してくださり、非常に良い手術を提供することができました。みんなの知識や情報を合体させてチームで新しいことにチャレンジできたのは嬉しく、また自信にもつながっています。
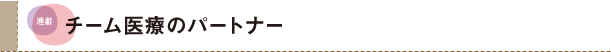
看護師(手術室)(後編)
一人前になるまで
――手術室看護師はどのくらい経験を積むと「一人前」と言えるのでしょうか?
和:どこまでできれば一人前と言えるかわかりませんが、一通りの手術看護ができるようになるのは、3年目くらいでしょうか。当院では、新人は器械出しのカリキュラムからスタートし、3つの科を約3か月ずつ回っていきます。半年ほど経つと外回りにも入り、さらにもう少ししたら、各診療科に分かれ、専門的な内容を学びます。2年目になると担当する診療科が決まってきて、3年目には当直ができるようになります。
高:診療科や先生によって手術の進め方は異なりますから、先生方一人ひとりの好みや癖まで含め、手術の流れを読むことが求められていると感じます。とにかく手術を何件も何件も見ているなかで、段々つかめてくる側面があります。
私は手術室で働いて9年になりますが、最近、今までにないくらい集中できたことがあったんです。長時間の手術で、普段なら集中力が切れてしまうような時間になっても、身体は動き、頭は冴えわたっていて。何も言われなくても、先生が次にどうしてほしいのかわかる気がする。今までにない感覚でした。
和:そういう時は、終わった後に術中のことを思い出せないくらい集中していて、チームと一体になっている感覚があります。後からどっと疲れますが、達成感もとても大きい。執刀医の先生に「今日は君がいてくれて良かった」と言ってもらえたときなどは、本当に嬉しいです。
手術はチームワーク
――手術においては、チームワークがとても大事なんですね。
和:はい。一人ひとりが、自分の目の前の作業にだけ集中していたら、手術はうまくいきません。周りをよく見てチームをフォローすることが大事ですね。
数時間も緊張状態が続く手術では、先生方も集中力が切れてしまうことがあります。そんなときは、術者や麻酔科の先生が見落としていることはないか気をつけたり、先生がイライラしていたら適切に声をかけたりするよう心がけています。そうした小さなことの積み重ねで、手術が円滑に進むかどうかが変わってくるのかなと思います。
高:看護師同士でも、チームでやっていくという意識が強いですね。ちょっと失敗しそうになっても、外回りと器械出しが、先輩後輩関係なくお互いにカバーし合う。いい手術ができるかどうかは、やはりコミュニケーションにかかっていますね。
――読者の医学生は今後、実習や臨床研修で手術室に来る機会もあると思います。彼らに伝えたいことはありますか?
高:私たちはチームの一体感を大切に、真剣に手術に臨んでいます。時々、見学中に雑談をしている学生さんも見かけるのですが、それではチーム全体に影響が出てしまいます。学生さんはどうしても見ているだけの時間が長くなり、集中するのが難しいとは思いますが、せっかく来ているのなら、手術に関心を持ち、少しでも多くのことを学んでいってほしいですね。
和:患者さんの移動や、重いものを運ぶときなどは、学生さんに声をかけると皆さん快く手伝ってくれ、とても助かっています。手術室の看護師は「怖い」と言われることもありますが、真剣に仕事に取り組んでいるからなんですよね。同じ手術室にいるときには、互いに助け合って、一緒に気持ち良く手術に関われればいいなと思います。
 今回お話を伺った看護師さん
今回お話を伺った看護師さん
和田 恵さん
日本大学医学部附属板橋病院
手術室看護師 18年目
 高橋 光さん
高橋 光さん
日本大学医学部附属板橋病院
手術室看護師 9年目



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:後藤 理英子先生
- Information:Spring, 2017
- 特集:看取りのあり方
- 特集:看取りの全体像 在宅の場合を例に
- 特集:人生の最終段階の経過
- 特集:病院で看取る
- 特集:家で看取る
- 特集:看取りを学ぶ
- 医科歯科連携がひらく、これからの「健康」④ これからの医科歯科連携を考える
- 同世代のリアリティー:大学職員 編
- 地域医療ルポ:秋田県横手市|山内診療所・三又へき地診療所 下田 輝一先生
- チーム医療のパートナー:看護師(手術室)
- 10年目のカルテ:皮膚科 飯沼 晋医師
- 10年目のカルテ:形成外科 佐野 仁美医師
- 10年目のカルテ:眼科 浪口 孝治医師
- 日本医師会の取り組み:日本医師会の医師賠償責任保険
- 医師の働き方を考える:患者のため、そして医療従事者のためにより良い制度を作っていきたい
- 医学教育の展望:学生の能動的な学びをサポートする
- 大学紹介:群馬大学
- 大学紹介:東京医科歯科大学
- 大学紹介:九州大学
- 大学紹介:和歌山県立医科大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- FACE to FACE:池尻 達紀×荘子 万能

