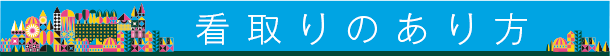
家で看取る(前編)
「自宅が病室」の総合病院
――内閣府の調査では、「治る見込みがない病気になった場合、どこで過ごしたいか」という問いに対し、「自宅」と答えた人が過半数という結果が出ています。在宅医療の担い手として、それに応えていくことは可能だと思われますか?
市橋(以下、市):ニーズに応えていくのは、決して難しいことではないと思っています。医療機器はコンパクトになり、病院の外でも十分使えるようになりました。電子カルテにより複数の医師で多数の患者さんを診ることができ、携帯電話でいつでも連絡がとれ、カーナビを使えば行ったことのない家にもたどり着けます。こうした技術の発達に伴い、病院の外であっても、質の高い終末期医療を実践できるようになっているんです。
喩えて言うなら、自宅が「病室」、携帯電話が「ナースコール」、道路が「廊下」、つまり地域全体を「屋根のない病院」にしていくことも可能だと思っています。
――病院では、医療資源の集約によって、24時間365日の診療体制を維持していますよね。先生は在宅で、どのように切れ目のない医療を提供しているのでしょうか。
市:現在当院には常勤・非常勤合わせて9名の医師、さらに看護師・管理栄養士・言語聴覚士・歯科衛生士・音楽療法士・理学療法士など、合計34名のスタッフが在籍しています。開業医が一人で在宅の看取りまで行うとなると、できる人は限られてきますが、私たちのようにチームで取り組むことで、負担の面からも専門性の面からも、実現可能性は高まると思います。
――確かに、様々な専門性を持つ人がチームを組むメリットは大きいですね。
市:在宅医療だからと言って、医学的判断が容易であるわけではありません。私は血液内科をベースにしていますが、他にも外科・泌尿器科・循環器内科・神経内科・緩和ケア・総合診療・精神科・皮膚科など、多様な専門性を持った医師が在籍しているので、難しい判断もチームで行うことができるのです。
――まるで総合病院のようですね。
市:在宅医療は、様々な制約があるなかで長期的に行う医療なので、介入の仕方によって患者さんの健康状態には大きな差が出ます。例えば余分な薬が一つ減るだけで転倒がなくなり、患者さんのQOLは大きく改善します。こうした複雑さに対応するために、医師だけでなく、多職種も含めた様々な専門家による「チーム医療」が有効なのです。
過ごしたい場所で過ごせるように
――自宅で療養することは、患者さんにとってどんなメリットがあるのでしょうか。
市:病院は基本的には治療する場所であり、生活を目的とした場所ではありません。同室の人の歯ぎしりやいびきでよく眠れない、処置やモニターの音が気になるなど、ゆっくり過ごすのに適しているとは言えません。また、出歩く場所もない、身の回りのことをする必要もない、話す家族もいないといった状況では、昼間もベッドに横になっている時間が長くなってしまうでしょう。夜は睡眠薬で眠らされ、昼間もベッドで横になっているとなると、様々な機能が低下してしまいます。
時折、住み慣れた家に帰ることによって奇跡的に良くなる人がいます。これは「食べて、寝て、出す」という健康にとって基本的な要因が整えられたことで起こる、当たり前の現象なのかもしれません。人は自分が過ごしたい場所で過ごすときに、幸せを感じるものです。生きている時間とは、死んでいない時間ではなく、好きなことをしている時間のことだと思っています。
ご本人やご家族が「自宅でも看取れる」ということを知らなかったり、近くにそれを支えられる医療機関がなかったりすることで、残された大切な時間を望む形で過ごせないことは避けたい。そんな思いで、在宅医療の推進に取り組んでいます。

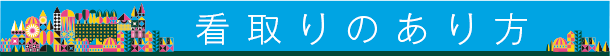
家で看取る(後編)
家で「看取る」ための様々なアプローチ
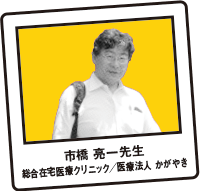
――先生は実際、どのくらいの件数の看取りに関わってこられたのでしょうか?
市:これまでに関わったがん患者さん541名のうち、約8割の436名を自宅で看取りました。今は、他の疾患も合わせると年間100名以上の方を看取っています。
――週に2名以上も看取っているということは、いつ亡くなってもおかしくない方を常に診ているということですね。
市:そうですね。ですから、病院と変わらない体制が必要です。使う薬剤も医療機器も病院と同様で、例えば一般的に病院で使う麻薬持続皮下注射のポンプも8台用意しています。
看取りの経験を積むことでスタッフの知識や技術も向上し、緩和ケア病棟に匹敵するような疼痛コントロールも可能になってきました。制度上は、医師や看護師が毎日訪問することも可能ですし、看護師が1日3回訪問することもあります。ご家族の負担が問題になる場合には、ショートステイやホスピスへの入院を併用しつつ、自宅での療養をサポートしています。
――看取りの際、ご家族や周囲の方の戸惑いはどうしてもありますよね。
市:最近は、家で人が死ぬということを経験したことがない方が多いので、僕たちは、患者さんが今後どのような経過をたどり、ご家族はどのように対応したらいいのかを詳しく書いた冊子を作り、ご家族にお渡ししています。痛がったり苦しんだりせずに亡くなっていくんだとわかると、皆さんずいぶん安心されます。周囲が起こりうる事態を予測でき、対応可能な状態にしておけば、多くの方が自然にご希望に沿う形で、お家で過ごすことができるんです。
――準備さえ整えば、自宅でも病院と遜色なく看取れるということですね。
市:ええ。時代の変化で人の価値観も変わり、病院で長く生きているよりも、自分が生きていたい場所で、しておきたいことをしたいという人が増えています。今はまだ、在宅医療は普通の選択ではないように思えるかもしれませんが、当たり前と感じられる日も遠くないと思います。




- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:後藤 理英子先生
- Information:Spring, 2017
- 特集:看取りのあり方
- 特集:看取りの全体像 在宅の場合を例に
- 特集:人生の最終段階の経過
- 特集:病院で看取る
- 特集:家で看取る
- 特集:看取りを学ぶ
- 医科歯科連携がひらく、これからの「健康」④ これからの医科歯科連携を考える
- 同世代のリアリティー:大学職員 編
- 地域医療ルポ:秋田県横手市|山内診療所・三又へき地診療所 下田 輝一先生
- チーム医療のパートナー:看護師(手術室)
- 10年目のカルテ:皮膚科 飯沼 晋医師
- 10年目のカルテ:形成外科 佐野 仁美医師
- 10年目のカルテ:眼科 浪口 孝治医師
- 日本医師会の取り組み:日本医師会の医師賠償責任保険
- 医師の働き方を考える:患者のため、そして医療従事者のためにより良い制度を作っていきたい
- 医学教育の展望:学生の能動的な学びをサポートする
- 大学紹介:群馬大学
- 大学紹介:東京医科歯科大学
- 大学紹介:九州大学
- 大学紹介:和歌山県立医科大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- FACE to FACE:池尻 達紀×荘子 万能

