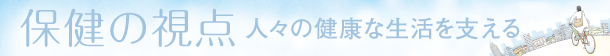
地域における健康づくりの取り組み(前編)
データからリスクのある人を見つけ、個別の関わりで「気付き」を促す
石川県能美市では平成20年度以来、糖尿病の重症化予防に、市と医師会、かかりつけ医が連携しながら取り組んできています。この取り組みについて、能美市医師会会長の松田健志先生、能美市健康福祉部健康推進課課長で保健師の川本素子さん、保健師の南芳美さんにお話を伺いました。
糖尿病重症化予防への注目
――この取り組みが始まった経緯を教えてください。
川本(以下、川):平成20年度より、40歳から74歳までの健康保険の加入者とその家族のうち、生活習慣病のリスクの高い人(いわゆるメタボリックシンドローム)を対象に、特定健康診査・特定保健指導が始まりました。これを受けて、能美市では糖尿病対策に重点的に取り組むことにしました。
――なぜ糖尿病に注目されたのですか?
川:市民の健診データによって、平成20年度以前から、血糖値・ヘモグロビンA1cが基準値を超える人が、県内でもかなり多い方であることがわかっていました。糖尿病治療者も年々増えており、40代以下の糖尿病治療者も少なくないという状況でした。
南:さらに、BMIや腹囲が基準を超えていない、いわゆる非肥満高血糖の方が多いこともわかりました。この方々は、特定保健指導の対象ではないのですが、いずれ糖尿病になるリスクがあると考えられます。
川:そこで能美市では、そのリスクを減らすべく、特定保健指導の対象とならない方へも保健指導を実施することにしました。
松田(以下、松):糖尿病は重症化するまで症状が出ないため、健診で所見があっても病院に行かない方も少なくありません。その結果、気付いた時にはかなり重症化してしまい、神経障害や腎症などの合併症を発症してしまうことがあります。そのリスクを減らすために、市と医師会、さらに専門医の先生方が協力して取り組んできました。
南:取り組みを始めるにあたり、まずは保健指導の対象者を明確化しました。市と医師会が話し合って、ヘモグロビンA1cが6・5%以上の方には医療機関を受診してもらい、5・6~6・4%の方には、市の職員による保健指導を行うことにしました。
住民の「気付く力」を支援する
――保健指導はどういう体制で行っているのでしょうか?
川:能美市では保健師と管理栄養士が指導にあたっています。保健師11名と管理栄養士2名、パートの栄養士2名の計15名でそれぞれ40~50名を担当しています。
――どのような働きかけをするのですか?
南:保健指導が必要な方に、できる限りご自宅を訪問する形で健診の結果をお渡しします。
川:住民が検査結果を理解するために、注目してほしい数値に色をつけて目立たせています。黄色は注意が必要な値、オレンジは医療機関を受診してほしい値といったようにです。数値に色がついていると、「どうしてだろう?」と考えてもらうきっかけになります。
住民の方から「どうしたらいい?」という言葉が出たら、私たちとしては「しめた!」という感じですね(笑)。それをきっかけに、普段の生活についてお聞きし、改善できる点を探していきます。
――「どうしたらいい?」が出てくるまで、様々な働きかけをするのですね。
南:そうです。すぐに質問してくださる方もいれば、なかなかその言葉が出ない方もいます。色々な方がいるので、相手を見ながら働きかけを変えています。糖尿病について説明するためのツールも色々あるんですよ。手を替え品を替え、その方に一番響く伝え方を探すんです。
川:他人から言われてやらされているうちは長続きしないものです。住民の方ご自身に「こうしよう」と決めていただき、かつ決めたことを尊重しながら関わっていかないといけません。ですから、相手の表情を見て、その方の気持ちを尊重した働きかけをすることが大事ですね。私たちがお会いして説明することで、住民の方々の気付きを引き出せたらいいなと思っています。
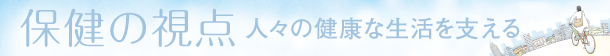
地域における健康づくりの取り組み(後編)
生活全体を見る視点
――医師の診療は基本的に医療機関で行われるのに対し、保健師は住民のもとに指導に出向くという違いがありますね。
松:そうですね。病院にいると、その方が来院したときの様子しかわかりません。糖尿病の予防や治療には、普段の食事や生活習慣が大きく関わりますから、改善のためには、生活の場に足を運んでの保健指導が重要だと思います。特に糖尿病は重症化するまで症状が出ないため、薬を飲んでも飲まなくても変わらないと思われやすく、経済的な余裕がない、病院に行く時間を取れないといった理由で、通院をやめてしまう方も多いのです。そういう方を保健師さんが拾いあげて、必要なときに医療機関につなげてくれるので、とても助かっています。
川:糖尿病に限らず、生活習慣病は全てその方の生活がベースにあります。仕事、嗜好品、食事、運動、生活リズムなど、長年の積み重ねが健診結果に表れてくる。疾患や症状だけを見るのではなく、生活全体を見る視点が重要だと感じています。
市と医師会との連携
――能美市では数年前から、市と医師会が連携して、地域の保健活動を推進しているのですね。
川:はい。平成24年の秋からは、「かけはしネットワーク能美」という、糖尿病の診療連携会議をスタートしました。
松:医師会が主体となり、病診連携方法の確立、研修会による医師会員への理解促進、住民への啓発等の活動を行っています。この活動が軌道に乗ったのは、地域医療に興味を持って熱心に活動してくれる専門医の先生方の力があったからでしょう。
川:毎月1回、医師会が主催して会議を行っており、45回を数えます。これだけの頻度で連携会議を行えていることは、能美市の強みだと思います。
南:かけはしネットワークを始めてから、医師会の先生方にも保健師がどんなことを得意としているのか理解していただけるようになりました。これからも密な連携を続けていきたいですね。


(写真右)「かけはしネットワーク能美」の会議の様子。
 |  |  |
松田 健志先生 | 南 芳美さん | 川本 素子さん |



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:大久保 ゆかり先生
- Information:Autumn, 2016
- 特集:保健の視点 人々の健康な生活を支える
- 特集:様々な場面における保健活動の実際
- 特集:地域における健康づくりの取り組み
- 特集:職場における健康づくりの取り組み
- 特集:誰もが自分の健康を主体的に獲得できる世の中へ
- 医科歯科連携がひらく、これからの「健康」① 口腔疾患の全身状態への影響
- 同世代のリアリティー:文系研究者 編
- NEED TO KNOW:山形県寒河江市「無事かえる」支援事業の取り組み
- 地域医療ルポ:熊本県熊本市|おがた小児科・内科医院 緒方 健一先生
- 10年目のカルテ:泌尿器科 眞砂 俊彦医師
- 10年目のカルテ:腎臓内科 岩永 みずき医師
- 10年目のカルテ:腎移植外科 岡田 学医師
- 医師の働き方を考える:医師の多様な働き方を受け入れる公衆衛生という職場
- 医学教育の展望:住民・行政と共に地域の未来を考える
- 医師会の取り組み:平成28年熊本地震におけるJMATの活動
- 大学紹介:金沢大学
- 大学紹介:東京女子医科大学
- 大学紹介:滋賀医科大学
- 大学紹介:長崎大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- 第4回医学生・日本医師会役員交流会 開催報告
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- FACE to FACE:廣瀬 正明×榛原 梓園

