シリーズ連載
医科歯科連携がひらく、これからの「健康」①
口腔疾患の全身状態への影響(前編)
「食べる」「話す」を支える口の機能を保つ
口腔内の機能
 ――「食べる」ことには、口腔内のどのような機能が関わっているのですか?
――「食べる」ことには、口腔内のどのような機能が関わっているのですか?
水口(以下、水):まず、「食べる」ことには、「咀嚼」と「嚥下」という機能と、これらの機能が発揮される場の環境としての「口腔衛生が保たれている」という重要な要素が関わっています。これらの口腔機能と口腔衛生は、加齢とともに衰えていく可能性があります。
口腔内のよくあるトラブルとしては、むし歯(う蝕)や歯周病があげられます。歯周病の有病率は、20歳代で約7割、30~50歳代では約8割、60歳代は約9割ともいわれています。これらの口腔疾患が直接命を脅かすことは滅多にありませんが、様々な病気のリスクを高めます。例えば歯周病は循環器系疾患や糖尿病、誤嚥性肺炎の大きなリスクファクターになることが知られています。また、放置された虫歯や、合わない義歯(入れ歯)は、咀嚼能力の低下につながり、消化器系に悪影響を及ぼすということも考えられます。
フレイルの悪循環に陥らない
――口腔内の健康状態は、全身の健康状態に関わってくるんですね。
水:そうなんです。また、「食事」は栄養を摂取するだけの行為ではなく、生活における「人とのつながり」の要素も持っているんです。家族や友人と食事をともにできる、ということがその人の社会生活、人生の豊かさを支えているともいえます。
近年は、口腔内の状態悪化が、社会生活の質の低下を招き、ひいてはサルコペニア(加齢性筋肉減弱症)や低栄養などによる機能低下につながる危険性が指摘されています。機能低下が進むと、最終的にはフレイル(虚弱)状態に陥り、要介護状態になってしまうでしょう。
――口内炎があるだけでも、食事が苦痛になると感じます。ずっと口に痛みがあれば、衰弱してしまうのも納得がいきます。
水:そうですよね。例えば、むし歯を放置し、義歯の不調を抱えた高齢者は、噛めない・痛いなどの理由で食事量が減ってしまう。すると栄養が足りなくなって全身の筋肉量が減り、活動量も低下する。活動量が低下すると、エネルギー消費量も低下する。さらに食欲が低下…という悪循環で、最終的にはフレイルが進行してしまうのです。
この悪循環に陥らないように、もしくは悪化を少しでも遅らせるために、歯科医師は様々な介入を行っています。歯周病やむし歯などを速やかに治療することはもちろん、定期的に口腔内の健康状態をチェックし、口腔衛生を保つことが重要です。
シリーズ連載
医科歯科連携がひらく、これからの「健康」①
口腔疾患の全身状態への影響(後編)
多職種連携の重要性
――悪循環に陥らないようにするためには、どんなことが必要なのでしょうか。
水:医科と歯科の連携が重要になります。口腔内の状態に問題がある高齢者の方で、歯科には受診していないけれど、何かしら医科の診療を受けている方は少なくありません。口腔の問題によって全身状態が影響を受ける前に、医科と歯科がうまく連携ができれば、フレイルの進行を抑えることができるでしょう。
――そのような連携は、少しずつでも進んでいるのでしょうか。
水:周術期管理としての口腔ケアの場面では、医科歯科連携の体制が構築されつつありますが、もう少し日常的な、義歯の調整や普段の歯磨きについての連携はまだまだこれから、というのが現状です。例えば、義歯が合わなくて食事が進まないという入院患者さんがいらっしゃった場合、歯科に頼ってほしいとは思っています。しかし、今の急性期病院の平均在院日数は2週間程度であり、全身状態が落ち着くと、すぐに転院・退院する状況のなかでは、歯科の治療を行う時間的余裕がないのです。
――では、退院のときにうまく地域の歯科医につなぐことはできないのでしょうか。
水:退院調整会議に歯科医師が入るのはかなり稀なケースで、よくて「おうちに帰ったら、かかりつけの歯科医師に診てもらってくださいね」と患者さんや家族に伝えるぐらいでしょう。しかし残念ながら、そう伝えても退院後の歯科治療にはつながらないことが多いです。ケアマネジャーや訪問看護師と病院との連携は進んでいますが、歯科はまだまだこれからなのでしょう。医科でリスクがある患者さんをピックアップして、適切に歯科が引き継いでいけるような体制を作っていくことが、今後の課題だと考えています。
――その他には、どのような職種と連携の可能性がありますか。
水:特に注目されているのは、管理栄養士ですね。歯の治療をするだけで寿命が延びるわけではもちろんなく、そこに管理栄養士さんも加わって栄養指導をセットで行っていく必要があります。口腔内の状態がよくなったら、どんな食事をすれば良いのか、栄養バランスが保たれているのかといったことを管理栄養士さんが指導することで、様々な病気のリスクが減少すると考えられます。
口腔疾患は、食べることや話すこと、笑うことといった感情表現に影響を及ぼし、精神的な健康にも大きく関わっています。WHO(世界保健機関)の定義によると、健康とは「単に病気がなく病弱でないというだけでなく、身体的、精神的、社会的に良好な状況」を指します。単に「病気でない」というだけでなく、QOLを保ってこそ、「健康」といえるのではないでしょうか。そのために、医科と歯科のみならず、様々な職種が連携して患者さんの「食べる」「話す」といった機能を支えていきたい。医学生の皆さんも、診療現場に出たときには、口腔内の健康状態にも関心を持ち、必要に応じて歯科との連携を考慮していただければ嬉しく思います。
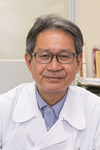 今回お話を伺った先生
今回お話を伺った先生
水口 俊介先生
東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 医歯学系専攻
老化制御学講座 高齢者歯科学 教授
特定非営利活動法人 日本咀嚼学会理事長
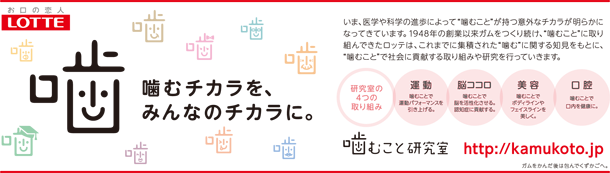



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:大久保 ゆかり先生
- Information:Autumn, 2016
- 特集:保健の視点 人々の健康な生活を支える
- 特集:様々な場面における保健活動の実際
- 特集:地域における健康づくりの取り組み
- 特集:職場における健康づくりの取り組み
- 特集:誰もが自分の健康を主体的に獲得できる世の中へ
- 医科歯科連携がひらく、これからの「健康」① 口腔疾患の全身状態への影響
- 同世代のリアリティー:文系研究者 編
- NEED TO KNOW:山形県寒河江市「無事かえる」支援事業の取り組み
- 地域医療ルポ:熊本県熊本市|おがた小児科・内科医院 緒方 健一先生
- 10年目のカルテ:泌尿器科 眞砂 俊彦医師
- 10年目のカルテ:腎臓内科 岩永 みずき医師
- 10年目のカルテ:腎移植外科 岡田 学医師
- 医師の働き方を考える:医師の多様な働き方を受け入れる公衆衛生という職場
- 医学教育の展望:住民・行政と共に地域の未来を考える
- 医師会の取り組み:平成28年熊本地震におけるJMATの活動
- 大学紹介:金沢大学
- 大学紹介:東京女子医科大学
- 大学紹介:滋賀医科大学
- 大学紹介:長崎大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- 第4回医学生・日本医師会役員交流会 開催報告
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- FACE to FACE:廣瀬 正明×榛原 梓園

