チーム医療のパートナー
看護師長(病棟責任者)
これから医師になる皆さんは、どの医療現場で働いても、チーム医療を担う一員となるでしょう。本連載では、様々なチームで働く医療職をシリーズで紹介しています。今回は、近畿大学病院で病棟責任者を務める副看護長、宇城恵さんと古川亮さんにお話を伺いました。
看護師長の仕事と役割
――看護師長(以下、師長)の業務内容について教えてください。
宇城(以下、宇):基本的に、ベッドサイドで患者さんのケアを行うのが看護主任(以下、主任)やスタッフナース(以下、スタッフ)です。その主任やスタッフの労務管理と人材育成を行うのが師長の役割です。近畿大学病院には、いわゆる師長に該当する病棟責任者が20名います。
また、ケアを行う際に必要な物品の管理と整理、病院の経営を意識しながらのベッドコントロールも師長の仕事です。
古川(以下、古):毎日の業務としては、日々の残業が適切か否かの確認や承認をします。月単位では、スタッフ人数分の勤務表を作成する仕事があります。労務管理は師長の役割の中でもとても重要で、働きやすく働きがいのある職場環境は常に目標としているところです。
――お二人が師長になるまでの歩みをお聞かせください。
古:看護師のキャリアには、現場のケアに幅広く対応できるジェネラリスト、専門看護師や認定看護師の資格を持っているスペシャリスト、そして管理職と、大きく分けて三つの道があります。
管理職を目指す場合、当院では日本看護協会が主催する認定看護管理者教育課程のファーストレベルという研修を受講します。その資格を持たないと師長になれないという決まりはありませんが、師長になる前後で受講するのが慣例になっています。
私の場合は、スタッフとして7年勤務し、その後主任となったのですが、病棟外での活動や、当時の師長と行動を共にすることが増え、管理業務への関心が増したことで師長を目指そうと考えるようになりました。
主任としては7年間勤務し、今年度から師長として働いています。師長になるまでの明確な年数は決まっているわけではありませんが、これくらいが平均的だと思います。
宇:私も、主任としての経験がきっかけで管理職を目指すようになりました。病棟運営を任されたことで、師長から管理的な視点で助言や指導を受ける機会が増えるうちに、そういう役割を担ってみたいと思うようになったのです。
また、私は主任になった後、摂食・嚥下障害看護認定看護師の資格を取得しています。認定看護師として多職種や他部門と連携しながら委員会活動などを通して、師長として組織横断的に関わっています。
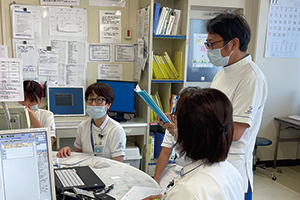

多方面との関わり
――看護師同士ではどのようなコミュニケーションを取っていらっしゃいますか?
宇:スタッフは若い人が多いので、髪型などちょっとした外見の変化やその日の体調などに細かく目を配り、コミュニケーションを取るようにしています。看護師という仕事は心身ともにハードなので、特に新人の変化は早めに察知することが大事です。また、患者さんのことで何か気になることがあれば、スタッフに声をかけて尋ねます。
主任とは、こまめに報告・連絡・相談をし、スタッフや患者さんについて常に情報共有するよう心がけています。特にお互いの不在時に起きたことについては念入りに行います。
古:他病棟の師長とは横のつながりを強く意識して、自分の知らないことがあれば積極的に訊きに行きます。特に病棟を移動する患者さんがいる場合、情報共有は必須です。
上司である看護部長と副看護部長は多くの病棟を束ねる存在なので、短時間での正確なコミュニケーションを心がけています。病棟にラウンドに来るときや自分が看護部に行く際に、簡潔に報告・連絡・相談するようにしています。
――患者さんと直接関わるのはどのような機会でしょうか?
宇:患者さんがスタッフに対して何か不愉快に感じたときや、同じ病室内の患者さんとの関係で相談があるときなどは、個別に直接対応しています。
古:患者さんの中には、ご高齢の方もいらっしゃるので、相手が自分よりも人生経験が豊富な方々であることを肝に銘じながら接しています。高齢者と接するのが不慣れな若いスタッフには、あえて患者さんとの関わり方を見せて手本を示しています。
――医師と直接関わるのはどのようなときですか?
宇:ベッドコントロールのとき、特に入退院や緊急入院の際には医師から直接相談を受けます。
また、患者さんは、医師には言いにくいことでも看護師には話せるということも少なくないため、スタッフからの情報を取りまとめて医師に伝えたり、逆に医師側からのスタッフに対する要望などを伝えたりといったパイプ役も務めています。
――他職種とはどのようなやり取りをしていますか?
古:高齢の患者さんは様々な疾患が複雑に絡み合っていることが多く、「今回はこの疾患を治療する」という方針を立てて入院してくることがほとんどです。そのため、どの科でも看護師は薬剤師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士と関わる機会が満遍なくあります。
他職種はそれぞれ専門職としての意見を持っており、相手の意見を尊重することがもちろん大切です。しかし、看護師は患者さんに最も近いところにいる職種です。そのため、師長として他職種の様々な意見を聞いて、調整しながらも、患者さんの気持ちに寄り添った判断をすることを心がけています。
看護師長ならではのやりがい
――師長の仕事のやりがいや醍醐味はどんなところですか?
宇:スタッフの日々の仕事ぶりを見ていて、成長を実感したときに一番やりがいを感じます。
また、笑顔で退院される患者さんを見るときは、師長としてだけではなく、看護師としてのやりがいを感じます。
古:患者さんにどのような看護を提供していくかを検討して、病棟の運営に直接携われるところが、難しいですが師長の醍醐味でもあると思います。
――最後に、これから医師になる学生に知っておいてほしいことやメッセージをお願いします。
宇:医師になると、手術などに追われて病棟にいる時間が減ってしまうので、学生や研修医の間に、看護師がどのように患者さんと接しているかを見ておいてもらいたいです。また、いずれ看護師に指示を出すようになる立場として、医師の指示を受けた看護師がどのように行動して、それが患者さんにどういう影響を与えるのかも注視してほしいと思います。
古:研修医のことは、患者さんも看護師も「医師」として、よく観察しています。特に患者さんは医師の態度に敏感なので、言葉遣いに気をつけて敬意を払ってほしいですね。社会性を身につけるためにも、ぜひ大学時代は様々な経験をしてほしいと思います。

宇城 恵さん
近畿大学病院 副看護長

古川 亮さん
近畿大学病院 副看護長
※取材:2022年11月
※取材対象者の所属は取材時のものです。



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:軍神 正隆先生
- Information:Winter, 2023
- 特集:シリーズ 臨床研修後のキャリアⅡ そして医師人生は続く
- 特集:XX年目のカルテ 開業医:坂野 真理医師
- 特集:XX年目のカルテ 病院院長:三石 知左子医師
- 特集:XX年目のカルテ 大学教授:大塚 篤司医師
- 特集:XX年目のカルテ 大学教授:藤巻 高光医師
- 特集:これから長い医師人生を歩み始める皆さんへ
- チーム医療のパートナー:看護師長(病棟責任者)
- Blue Ocean:秋田県|松本 奈津美先生(男鹿みなと市民病院)
- Blue Ocean:秋田県|阿部 寛道先生(羽後町立羽後病院)
- 医師の働き方を考える:産婦人科医 柴田 綾子先生
- 日本医師会の取り組み:医学部卒後5年目まで会費減免期間を延長します
- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:大阪医科薬科大学「学生研究」
- 同世代のリアリティー:スポーツ科学研究者 編
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- 医学生の交流ひろば:MedYou Labo
- 医学生の交流ひろば:Dendrite
- 医学生の交流ひろば:鹿児島大学プライマリ・ケアサークル KAAN
- 医学生の交流ひろば:全国医学部ミニキャン&ご馳走の旅
- 医学生の交流ひろば:札幌医科大学 PQJ 2023 運営委員会
- 医学生の交流ひろば:医学生・医師が答えるみんなの疑問 Q&A
- 医学生の交流ひろば:医学生座談会~CBTを終えて~
- FACE to FACE:井上 敬貴×伊東 さら×ダン タン フイ

